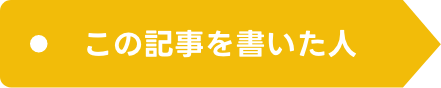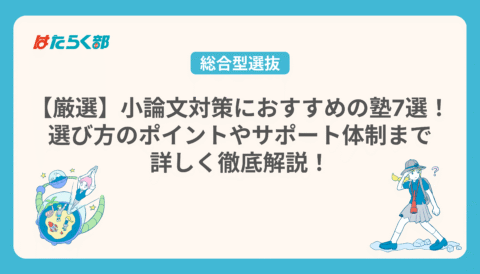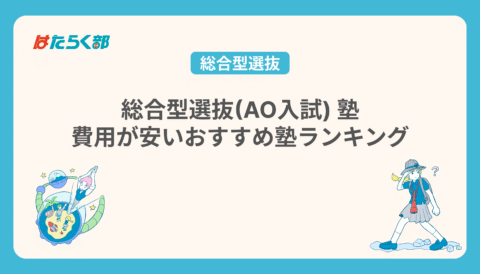ブログBlog
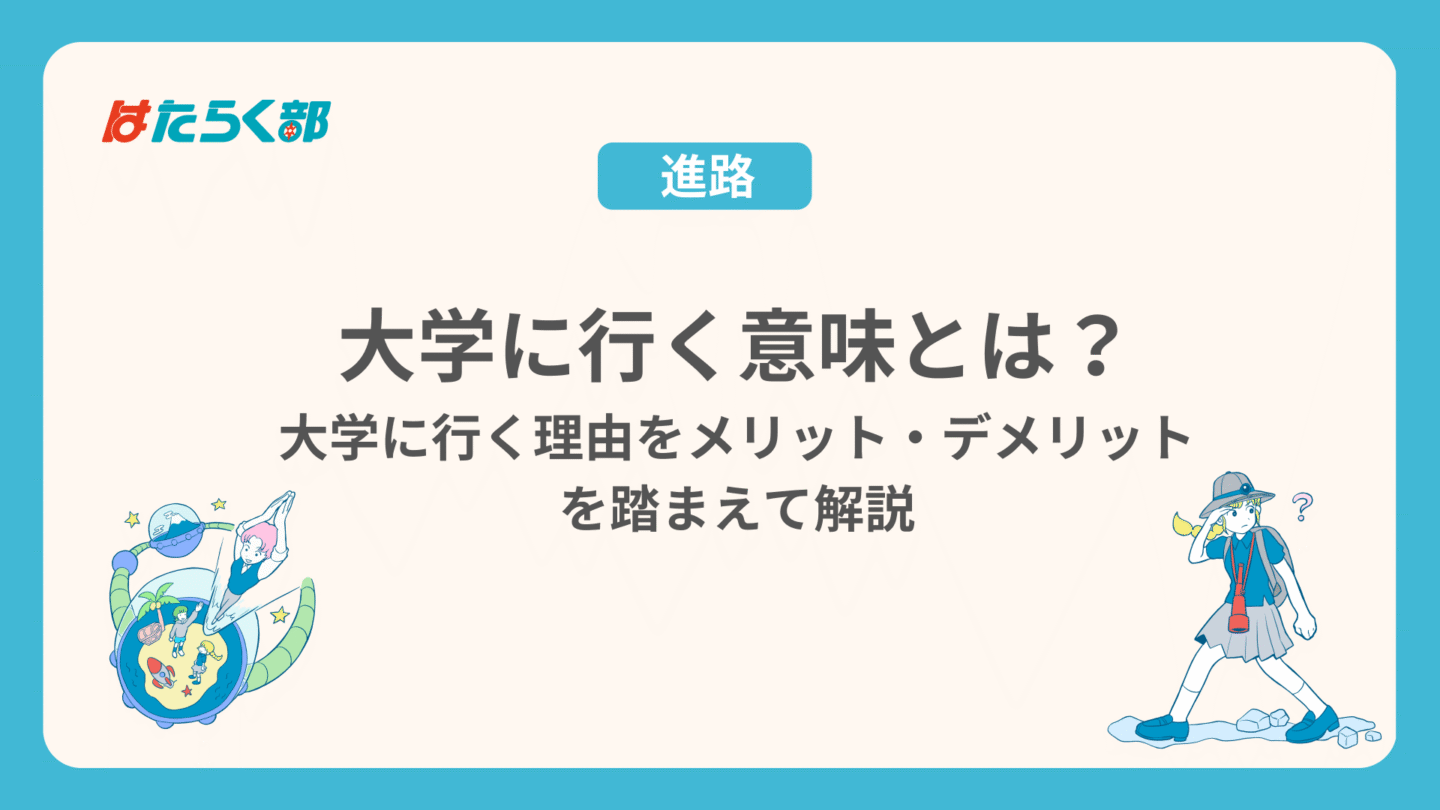
大学に行く意味とは?大学に行く理由をメリット・デメリットを踏まえて解説

「大学に行く意味が分からず、高校卒業後に大学に行くべきか分らない、、、」「なんとなく高校卒業後は大学に行こうと思っているけど、はっきりとした理由もなく、本当に正しい選択なのか不安、、、」
「大学生活を送っているけど社会人として活躍することに繋がっている感じがせず、将来を見据えてどのような大学生活を送るべきか知りたい」
このように考えた経験がある人も多いのではないでしょうか。現在の大学進学率は約60%と半分以上が大学に進学していますが、果たしてそのうちどれくらいの人が大学に行く意味をしっかり考えて進学できているでしょうか?多くの人が「周りが大学に行くから自分も、、、」という考えで大学進学しているでしょう。ある意味、高校で大学進学までのレールが敷かれている感じがしますね。。。
と言いながら、そういう私自身も「東京に行きたい」という単純な理由で大学を目指していましたが、今振り返れば社会人としての活躍を見据えた上で、大学生活にどういう意義があるのか、自分で納得して大学進学を目指した方が、受験へのモチベーションも上がるし、進学後もより充実した大学生活を送れたなぁと感じています!
今回は、大学に行く意味が分からない人たちのために、「大学に行く意味」や「大学に行くメリット・デメリット」「大学以外の選択肢」について自分自身の経験を踏まえながらお話しします。「大学に行く意味」を自分自身で納得して頂き、進路選択やより意義ある大学生活の参考になれば幸いです!
大学に行く意味とは?
興味のあることを最適な環境で4年間専門的に学べる
そもそも大学は、研究の役割がメインなので、研究したい人が行くべき場所です。
高校までの大学受験向けの学習よりもかなり専門的な学習をすることになります。
また、その分野の第一線で研究している教授や講師から学んだり、研究に携わったりすることもできます。
また大学の図書館には様々な分野の専門書籍や論文があります。これらの書籍や論文を社会人になってから読もうと思ってもなかなか難しいです。
学問を追究したり、教養を身につけたりしたい人にとっては大学は最高の場所ですね!
ただ大学での学びが直接仕事に繋がるという保証は全くありません、というか直結してる方が少ないです。
例えば工学部を卒業して製造業の会社に就職したとしても、経理部に配属されてしまったら、自分だったら「何のために勉強してきたんだろ、、」と思ってしまいます、、、。
大学での学びをより直接的に仕事で活かしたい場合は、大学院に進学してより専門性を高めるのが良いと思います。
大学生だからこそ経験できることがある
学生の本分は学業と言いますが、学業以外にも大学生だからこそ経験できるようなものがたくさんあります。
例えばサークル活動で、共通の趣味や興味のある人々で集まって定期的に活動を行います。
「別に大学の外でも自分の趣味に合ったコミュニティに入れば同じじゃない?」と思う人もいるかもしれませんが、大学だからこそのメリットがあります。
小中高は同じ場所に住んでいたという理由で同じ学校にいるという可能性が高いです。
しかし大学ではその大学の特徴に沿った人たちが集まりやすいですね。
例えば筆記試験の難易度が高い大学では勉強ができる人が多く集まり、スポーツが強い大学では、スポーツが得意な人が多く集まり、起業家を育成する大学では起業したい人が多く集まります。
ある意味高校生の時よりも選択肢が狭まっているんですが、逆に言えば大学では「今まで頑張ってきたこと」「やりたいこと」といった共通点が多い人と会える可能性が高いということ。
なので、居心地もいいし、一生の付き合いになる友達やパートナーに出会えることもあります!
その意味では、大学は利害関係のない友達を得られる最後の場所なのかもしれないですね。
私の所属する東京大学ではサークルが約300個あり、とても多く感じますが、多い大学だと3000個以上もあるそうです!
ちなみに私もマジックサークルなどに入っており、日々楽しく活動しています!
自分の行きたい大学にどんなサークルがあるのかを調べるだけでも、受験のモチベーションが上がりそうですね!
サークル以外にも交換留学やゼミなど、大学生だからこそ経験できることはたくさんあります!
新たなものや人に出会い、視野が広がる
高校までは住んでいる場所が同じで年齢が同じ人と過ごす場合が多いですが、大学では今まで出会ってこなかったタイプの人たちとたくさん出会えます。
私は九州の佐賀県出身なのですが同じ九州出身の人は同じクラスに一人しかいませんでした。
就職すれば基本的に年齢も出身も大学も異なる人とコミュニケーションをとっていく必要がありますが、大学でその予行練習ができるのではないでしょうか。
自身の生活環境を変えることができる
生活面では大学進学後、実家を出て1人暮らしをする学生はこれまでとは違う土地に住むことになります。
掃除・選択・自炊など自分のことは全て自分で行わなければいけないので、大変かと思いますが、生活力を養えたり、計画的に生活する面白さがあります。
そういう点で自分を取り巻く生活環境を変えられるのはメリットと言えます。
キャリアの幅が広がる
医者や薬剤師、大学教授、研究者、国家公務員といった大学に行かないとなれない職業は少なくないです。
また、法曹や公認会計士、大企業の総合職は大学に行っていないとなるのが難しいでしょう。
さらに大学卒業を採用条件にしている企業や公務員試験が多く存在するので、就職の幅も広がります。
国内最大級の高校新卒向けの求人サイトはジョブドラフトNaviで、掲載企業数は2,354社(2023年度12月)なのに対して、大学生向け大手求人サイトのマイナビは掲載企業数が30000社以上と、単純比較しても大卒向けの求人の方がかなり多いことが分かります。
大学に行く意味を見出せない理由とは?
やりたいことが見つからない
高校までの学びは国語、数学、理科、英語、社会など大学受験を目標にしたものであることが多く、実際に自分が将来仕事にしたいことについて考える機会は少ないです。
何がやりたいか決まっていない状態では、大学に進学する目的がはっきりしていないので、大学に行く意味が分からなくなってしまいます。
これは自分自身だけの問題ではなく、高校の進路指導の影響が大きいのではないでしょうか。
高校にとって進学実績は「3年間の教育活動の成果」を示すものであり、進学実績が良いほど翌年多くの生徒が募集するし、学校の知名度も上がります。
だからこそ、高校側も生徒側も大学受験という本来通過点でしかないものがあたかもゴールであるかのように捉えてしまいます。
日本の教育改革の一つとして「高大接続改革」というものがあります。
これは、2015年に文部科学省によって発表された「高大接続改革プラン」をもとに、高校教育と大学教育・入試をより密接に連携させることで、多様な学力や能力を評価できる教育制度を目指す取り組みです。
「学力の3要素(1.知識・技能、2.思考力・判断力・表現力、3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)」を育成・評価するための一体的な改革とされています。
これにより、確かにグローバル化の進展、技術革新、国内における生産年齢人口の急減などの激しい社会状況の変化の中で、新たな価値を創造していく力を育てる方向に教育が向かっているとは思いますが、大学受験のシステム自体はあまり変わっていません。
「とにかく大学受験を頑張るのが正解だから、それに従って勉強しないといけない」という意識も残っている。
そのような環境でやりたいことを見つけるのは難しいので、あなただけのせいではないですね。
だからといってそのままにしていてはやりたいことは見つからないので、将来のキャリアや大学でやりたいことを考える機会を積極的に作る必要があると思います。
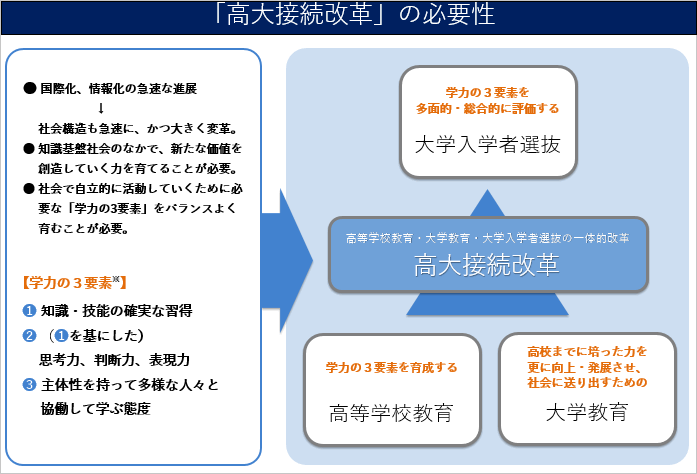
高大接続改革の必要性
出典:高大接続改革:文部科学省
自分の好きなことがわからない
大学進学の際は学部学科まで決めて進学することが多いですが、そもそも大学受験のための勉強だけでは、各学部学科の学問の内容や特徴について解像度が低いままであり、自分の好きな分野が分からない状態で受験を迎えてしまう人も多いのではないでしょうか。
自分の好きなことと大学での学びが直結していないことで、大学に行く意味が感じられなくなってしまいます。
高校生の時点で自分の興味のある分野がどうしても定まらない場合は、入学して最初は様々な分野を学ぶことができ、その後学部学科を選ぶことのできる制度がある大学に進学するのがおすすめです。
例えば東京大学、国際基督教大学(ICU)などが挙げられます。
その分、入学後に行きたい学部にいくために勉強し続けなければならないですが。
また、このような制度のある大学は難関大学であることが多いので、今のうちから勉強するのが良いと思います。
大学の選び方が分からない
日本には大学が約800校あり、立地や学費、学部学科、入試方式など様々なことを考慮して大学を選ぶ必要があります。
選択肢が多すぎて、どの大学に行くべきか分からない人も多いのではないでしょうか。
気になる大学は資料請求をしたり、オープンキャンパスに行ったりして、進学後の大学生活のイメージを掴みましょう。
その大学に進学した先輩がいると、リアルな声が聞けてとても参考になるかもしれません。
大学に行く以外にもたくさん選択肢がある!
専門学校に進学する
専門学校では、特定の職業スキルや資格取得を目的として、実践的な学びを得られます。
期間は1~3年で、美容師、調理師、看護師、保育士、ゲームクリエイターなどがあります。
現場で通用する技術や資格が取得でき、卒業後すぐに就職につながりやすいのが良い点です。
留学する
例えば英語圏での語学留学やワーキングホリデーなど海外で学んだり働いたりすることで、語学力だけでなく異文化理解やグローバルな視点を得ることができます。
留学によって身につけた語学力やグローバルな視点は、就職の際に有利に働きますし、将来海外で仕事をしやすくなるといったメリットがあります。
仕事する
高校卒業後すぐに社会に出て働くことで、さらに大学の学費がかからずに、早くから実務経験を積むことができます。
大卒の人より4年早く社会人として自立できることは大きなメリットではないでしょうか。
ギャップイヤー
ギャップイヤーとは進学や就職の前に、自分の興味や方向性を探すための自由な時間で、1年程度、旅やボランティア、インターンなど社会体験活動を行うことを言います。
もともとイギリスで始まった制度で、欧米では習慣として根付いており、アメリカのオバマ前大統領の長女マリアさんが、ハーバード大学への入学前に1年間のギャップイヤーをとったことで話題になったこともあります。
学生が何のしがらみもなく、自分の自由意思でやりたいことを見つけて、集中して取り組める貴重な時間であり、自分のやりたいことを見つけるきっかけになるのではないでしょうか。
大学に行かないことで得られるメリットとは?
早くから社会経験を積める
高校卒業後すぐに就職すれば、同年代よりも早く職場での経験を積むことができます。
先に社会経験を積んだ後に大学で学ぶことで、より深い学びを得ることもできると思います。
大学に必要な学費がかからずに済む
大学4年間での学費は国立でも約250万、私立文系であれば約400万円、私立理系であれば約550万円ほどかかります。
大学卒業後も奨学金の返済を続ける人も少なくない中、このような負担がなく済むのは大きなメリットではないでしょうか。
長期の旅行などに時期・期間の制限がない
大学生活では授業や試験のスケジュールに縛られますが、進学しなければ自由度が高まります。
長期旅行や世界一周など、数か月〜1年以上の計画も可能になり、海外ボランティアやワーキングホリデーなど、まとまった時間が必要な経験がしやすく、自分のペースで人生設計を立てられます。
大学に行く意味が分からない、、、では大学に行かないことで想定されるデメリットは?
大手企業の正社員採用に応募できない時がある
多くの大手企業や有名企業の総合職採用では、「応募条件:四年制大学卒業以上」としている場合があります。
例えば総合職、企画職、研究職などは大卒以上が必須条件のことが多いと推測できます。
例を挙げると、最大級の高校新卒向けのジョブドラフトNaviの企画・マーケティングの求人は6件※1であったのに対し、大卒向けの求人サイトのマイナビの企画職の求人は9160件※2でした。
もちろんこれだけで一概には言えないですが、大卒の求人の方が高卒の求人の方がかなり多いという傾向があると考えられます。
※1:ジョブドラフトNaviサイト内の職種のうち企画・マーケティングに絞り込みして検索
※2:マイナビサイト内の職種のうち調査研究・マーケティング、経営企画、企画・商品開発に絞り込みして検索
大卒と比べて給与条件が不利になることが少なくない
学歴によって初任給や昇給条件に差がある企業は少なくありません。
高卒と大卒で初任給に数万円の差がつくケースも多く、ユースフル労働統計2022-労働統計加工指標集-によると大卒の生涯賃金が男性:2億7千万円、女性:2億2千万円に対し、高卒の生涯賃金は男性:2億1千万円、女性1億5千万円と大きく差があります。
また、出世スピードに差が生まれる可能性があります。
令和元年賃金構造基本統計調査結果をみると大卒の初任給が21万200円に対し、高卒は16万7,400円という結果でした。
その後の年齢別の平均賃金を見ても、年齢を重ねるにつれて大卒と高卒の幅は大きくなっています。
このように大卒と高卒の平均賃金の違いを考えて、「とりあえず大学に行こう」と思う人も多いのではないでしょうか。
企業は大学生に何を求めてるの?
前提として、大卒のほとんどが企業に就職します。
95%以上です。
大学が就職予備校化しているとも言われます。
企業視点からみた大学に行く意味とはなんでしょうか。
企業は人材に何を求めているのでしょうか。
もちろん職種によって求められる能力は大きく異なりますが、多くの企業に共通して求められる能力があるのではないでしょうか?
まず何といってもコミュニケーション能力でしょう。
企業では、年齢も性別も考え方も異なる人との関わりばかりですし、チームワークが求められます。
そのような中で結果を出すには、相手の話すことを理解して、相手が理解できるように説明することが大事だと思います。
また、与えられた仕事をこなすだけでなく、期待以上の行動を起こす積極性も求められるでしょう。
他にも、問題解決能力や協調性、誠実性など。
いずれにせよ大学卒業後就職するほとんどの大学生にとって、これらの能力をインターンシップや大学での研究発表などを通してレベルアップさせていくことが大切です。
意味のある大学生活を送るために大切なこと
「大学に行く意味が分からない、、、」と悩んでいる人も多いと思いますし、実際私もそう思ってしまうことがあります。
意味のある大学生活を送るためにはどうすれば良いのでしょうか?
そもそも大学へ行く目的は人それぞれですよね。
例えば、将来研究者になるために大学に行く人もいるし、「大学は人生の夏休み!」という気持ちで大学生活を楽しむために大学に行く人もいます。
もちろん人生のモラトリアムである大学生活を楽しむのはめっちゃ大事だと思うんですが、楽しんでいるだけだと就活の時に「ガクチカ」を持っていなかったりと後々後悔するかもしれません。
大学は高校と比べて急に自由な時間が増えるので、自分の将来のキャリアから逆算して今やるべきことも自分で考えて行動しつつ、大学生活を楽しむのが大事だと思います!
ただ周囲が行っているからと漠然と進学するのではなく、自分なりの意味を持って入るようにしてください。
「自分は大学に行って何を学びたいのか」「大学に行くことで成し遂げたいことは何か」を明確にすることで、有意義な大学生活を送れるでしょう。
意味のある大学生活を送りたいならはたらく部がおすすめ
私は高校生の時、「大学受験の勉強は大学に入るためにやってるけど、本当にこれだけでいいのかな、、、」と不安を感じていたことがあります。
特に勉強が嫌いなわけではなかったけど、「周りがやってるから」「周りが大事というから」という風に勉強が目的になっていた気がしています。
そんな中、はたらく部の広告を目にし、自分の性格について知ったり、社会の仕組みについて知ったり、社会人と話す機会があったりと、社会の先取り体験ができるのがおもしろそうと感じ、入部しました。
私は今まで同じ場所で育ってきたので、その地域内の友達しか基本いなかったのですが、そんな中はたらく部で様々な社会人に出会ったり、関東や近畿、四国といった日本全国の同級生や先輩に出会ったりできたのはとても新鮮な体験でした。
その後も企業課題解決コースで、はたらく部の部員とともにサービスのアイデアを企業の方にプレゼンしたり、Youtubeでビジネスアイデアのプレゼンを行ったりと、うまくできていたかに関わらず、少しでも社会の先取りになるような体験ができたのかなと満足しているし、人前でプレゼンするという自信にもつながりました。
このような体験をしたことで、私は社会人として活躍したいという志の高い友達とたくさん出会うことができたし、現在もはたらく部インターン生として活動させてもらっています。
私と同じように「勉強だけしてて本当にいいのかな、、」「もっと社会のことについて知りたい!」と思う人はぜひはたらく部の無料体験に申し込んでみてください!

木原汰一郎
はたらく部一期生として活動後、はたらく部を運営する株式会社RePlayceにインターン生として参加。高校時代は「東京に行きたい」という思いで学業に励み、その後、東京大学理科一類に進学。はたらく部では企業課題解決コースやプレゼンバトルなどに挑戦した。インターン業務では広報用記事の作成に取り組んでいる。