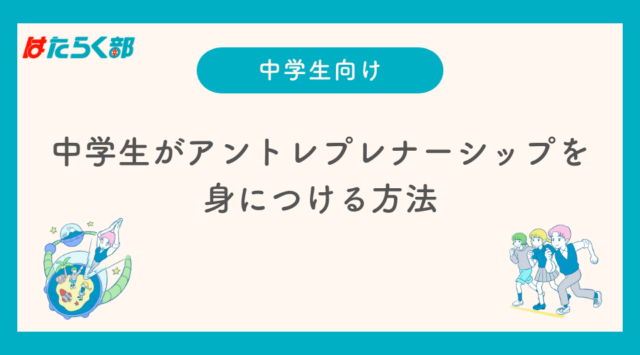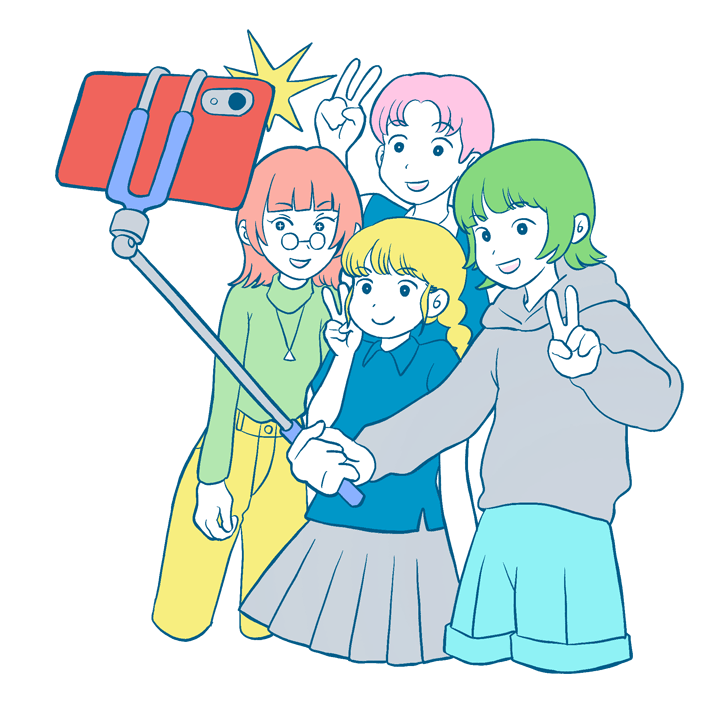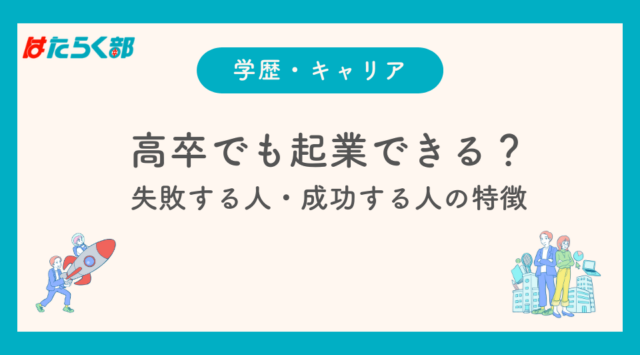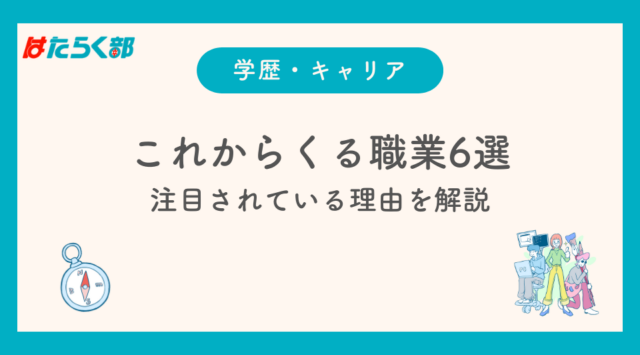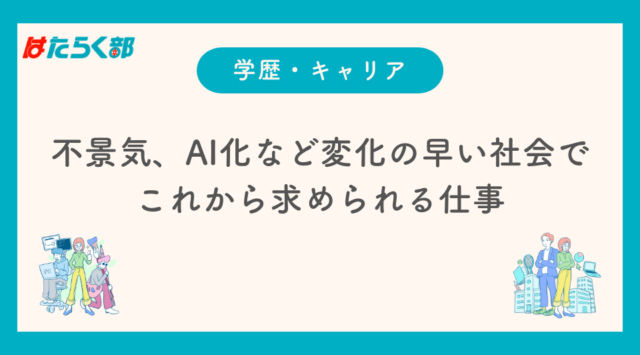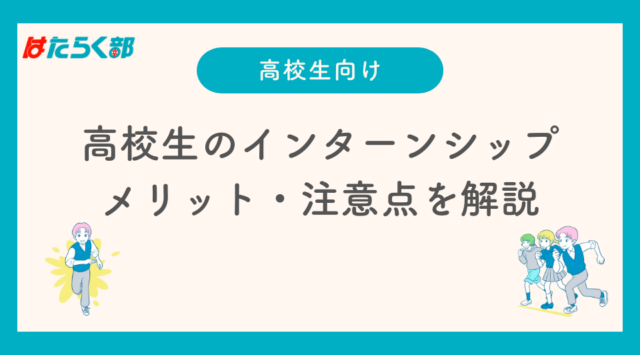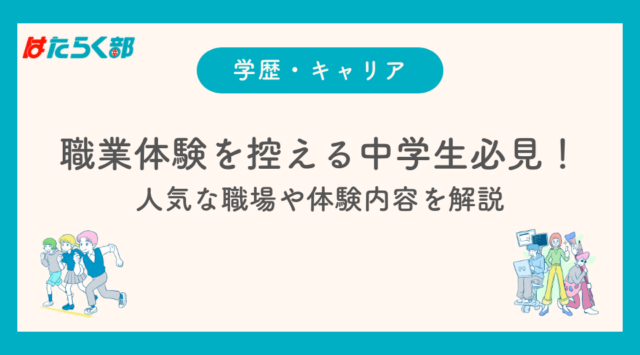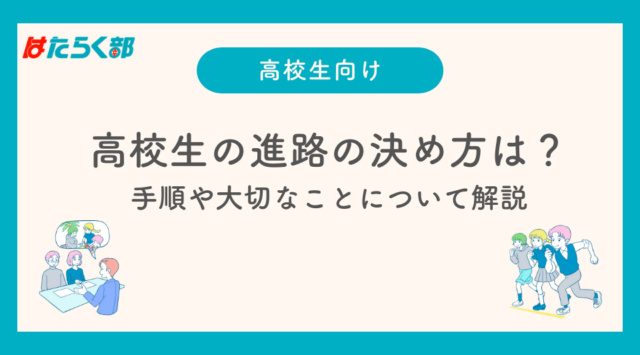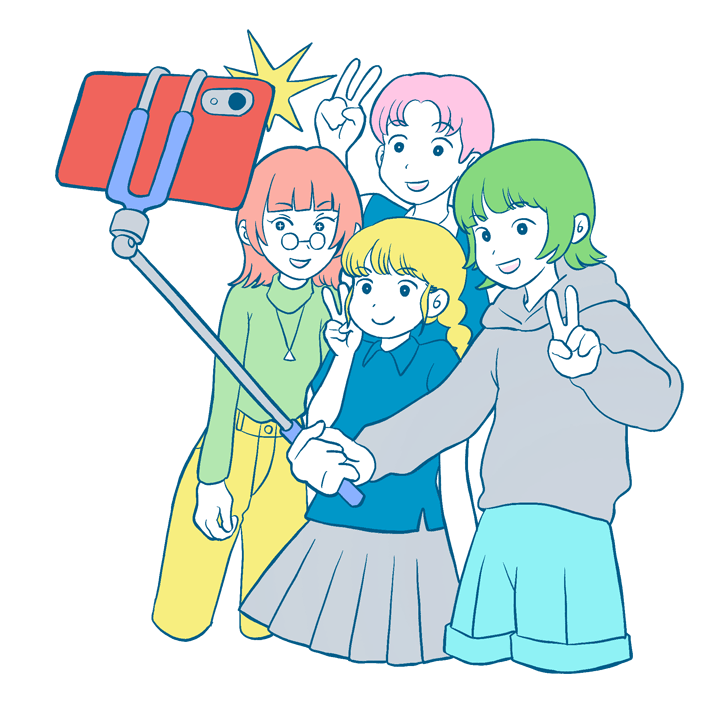
Blog
![alt]()
高校生にアントレプレナーシップが求められる理由と背景
ナレッジ
変化の早い現代社会では、高校生にも自主的に行動できる「アントレプレナーシップ」が求められるようになってきました。アントレプレナーシップとは、「起業するための精神」ではなく、今までとは違う機会や変化に自ら飛び込み、自分自身で新しい何かを創り出すことができる力のことを指します。本記事では、アントレプレナーシップの基本から身につける方法まで説明します。最近、アントレプレナーシップという言葉がよく聞かれるようになってきました。社会人やビジネスの世界だけの話だと思われがちですが、高校生の皆さんにとって決してほど遠いものではありません。今回は、アントレプレナーシップの基本から高校生が身につける方法を紹介します。アントレプレナーシップとはアントレプレナーシップを日本語に訳すと「起業家精神」という意味になります。経営学者のピーター・ドラッカーはアントレプレナーシップを「イノベーションを武器として、変化の中に機会を発見し、事業を成功させる行動体系」定義しており、ハーバード大学の教授であるハワード・スティーブンソンは「コントロール可能な資源を超越して、機会を追求する精神」としています。アントレプレナーシップは「起業するための精神」ではなく、今までとは違う機会や変化に自ら飛び込み、自分自身で新しい何かを創り出すことができる力のことを指します。高校生であっても日常生活のなかで身につけることができます。身につく能力アントレプレナーシップによって身につく能力は大きく分けて3つあります。高校生の皆さんも部活動や学校行事、勉強など普段の生活でこれらを実践できないか考えてみてください。 1.チャレンジ精神1つ目は、チャレンジ精神です。情熱や初めての体験やリスクを恐れない心が身に付きます。アントレプレナーシップが身についている人は、どんな出来事もポジティブに捉える事ができ、失敗も新たなバネとなります。 2.起業家的能力2つ目は、起業家的能力です。起業家として事業を設立したり、売り出したりすることができる能力が身に付きます。例えば、課題発見力・コミュニケーション力・論理的思考力・情報収集力などが挙げられます。自ら課題を発見し論理的に考え、周りを巻き込んで形にすることが可能です。部活動や学校行事などあらゆる場面で、意識してみましょう。 3.ビジネススキル3つ目は、ビジネススキルです。アントレプレナーシップが身についている人は、経済活動がどんな仕組みで動いているのか、どんな考え方をもって行動しているのか理解できます。そのため、実際のビジネスに近い経験ができれば、実務の知識も自然と身についていきます。仕事についていなくとも、ニュースなどをみて、考えることはできます。疑問に思うことがあればなんでも調べてみましょう。アントレプレナーシップが求められる背景なぜ私たち高校生にもアントレプレナーシップという言葉が聞かれるようになり、求められるようになったのか、その背景について説明します。成果主義これまでの日本の企業は、日本型雇用と言われる終身雇用や年功序列が主流でした。しかし、近年は業務による成果によって給料やキャリアが決まる成果主義を取り入れる起業が増加してきています。社長や上司から言われたことをこなすだけではなく、自ら行動しなければ、十分な給料や目指したいキャリアをつくることは難しいでしょう。雇用の多様化成果主義と同様に雇用形態も広く複雑になってきています。会社に務めるだけではなく、フリーランスとして個人と企業の契約をもって仕事を得ている個人事業主や自ら起業して社長になる人もいます。副業としてフリーランスになる人もいます。雇用が多様化していることにより、枠にはまったはたらき方ではなく、自ら責任をもって仕事をこなしたり、仕事量や仕事内容を管理することが必要です。グローバル化グローバル化によって、新たな商品が諸外国から入ってきたり、SNSなどのインターネットサービスで新たな価値観がすぐに共有されるようになったりと、モノや情報が多くなっています。変化がはやく複雑化した現代で、正しい情報を見極めたり、多様な価値観を理解できる人材が求められています。 なぜ高校生にアントレプレナーシップが必要なのかではなぜ高校生にアントレプレナーシップが必要なのでしょうか。社会人だけでなく私たち高校生がアントレプレナーシップを身につけるべき理由について説明します。自主的に行動できる人材が求められているから高校生になるまで、人から言われて行動したり与えられたものだけやっていけば良かったのですが、今後は自分で情報を集め行動していかなければなりません。高校生の皆さんにとって重要な進路選択にあたっては、自分がどんな人間になりたいのか、どんな選択をしなければならないのか自分で決める必要があります。また、自主的に行動できるスキルは社会に出てから自然と身につくものではありません。チャレンジしてみる行動力と失敗をバネに再挑戦できる忍耐力は高校生のうちから身につけることで、社会に出て大きな成果を出せる人材として活躍することができるのです。社会の不変性に対応できるようになるためもう1つの理由としては、グローバル化が進んだことで様々な情報が飛び交い、技術の変化も速くなっています。社会の動きを捉え、複雑に変化する世の中に対応し続けられるのはアントレプレナーシップをもった人間です。情報を取捨選択し、課題を見極め、最適な解決策を導き出すことは簡単ではありません。この力は、高校生活で何かを決めなければいけないときや課題を解決するときに役立ちます。高校生のうちからアントレプレナーシップを意識していけば、将来大きな壁にぶつかった時も乗り越えられる力が身につきます。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} アントレプレナーシップを身につけるためにこれまで、アントレプレナーシップの基本や必要な理由について解説してきました。では、高校生がアントレプレナーシップを身につけるにはどのような方法があるのでしょうか。読書1つ目は、読書です。アントレプレナーシップに関する本でアントレプレナーシップの基本から応用まで学ぶことが可能です。また、ビジネス書や自己啓発本などから、著名人の実践的なアントレプレナーシップの知識を取り入れることも可能です。高校生向けに書かれたアントレプレナーシップの本も出版されているため、初めて読む人には易しい本から読むのをおすすめします。学校教育2つ目は、学校教育です。学校の授業の一環としてアントレプレナーシップを学んだり、アントレプレナーシップを育む教育課程にアレンジしている学校も存在します。しかし、すべての高校がアントレプレナーシップの教育を導入しているわけではありません。もし、自分が通っている学校でアントレプレナーシップが身近でないと感じる高校生がいたら、学校の行事や委員会のリーダーなどに積極的に手を挙げてみてください。立候補するという行動だけでもチャレンジ精神が育ち、責任感を持って役を勤め上げれば、アントレプレナーシップが身につきます。高校生活の中にもチャレンジするきっかけはたくさん転がっています。アントレプレナーシップ・プログラムの参加3つ目は、高校生向けのアントレプレナーシップ・プログラムに参加してみることです。学校教育では十分な学びが得られないことも多々あります。そんな時は民間の企業が開催するイベントや教育プログラムに参加することで十分にアントレプレナーシップを学べます。将来の選択肢として起業も考えてみよう高校生にとってアントレプレナーシップを身につけることはとても身近で効率的な成長方法です。将来は、会社員になるという選択だけでなく、自分の力で会社を立ててみるという選択肢も自然と出てくるのではないでしょうか。今からアントレプレナーシップを身につけ、周りの高校生と差をつけていきましょう。
READ MORE
![alt]()
高卒でも起業できる?日本の起業成功率と失敗する人・成功する人の特徴
ナレッジ
一般的に起業の成功率には、高卒も大卒も関係ないといわれています。日本には高卒の起業家もたくさんいます。本記事では起業の成功率に関するデータを参考に、事業を成功に導くためのポイントを解説します。失敗しやすい人と成功しやすい人の特徴もそれぞれ紹介します。起業の方向性について見直したり、自分の強みを探したりする指標になるはずです。データから読み解く「高卒で起業した場合の成功率」「高卒で起業した場合の成功率」についてのデータはありませんが、開業・廃業の状況は国が調査し公表しています。結論、起業に学歴は関係ありません。就職なら大卒者が有利とされていますが、誰にも雇われない起業なら、高卒が選考の不利になるということはないでしょう。高卒で起業した場合の成功率は気になりますが、個人の努力や環境、運なども関係してくるのが起業の成功有無です。まずが、産業別の廃業率や起業後の存続率をみてみましょう。データを参考に、起業の成功率を高めるための方法を探っていきます。起業後の年数ごとの存続率起業後の会社の存続率は、設立から3年で60%ほど、10年で6%ほどといわれています。過半数の会社が、起業から3年以内に廃業していることになります。まずは存続しなければ成功もない、と考えると、3年を目安とした際に「起業の成功率は低い」ということを踏まえ、どんな事業を起こすか、起業するのかどうかを慎重に考えましょう。日本の開業率・廃業率の推移
READ MORE
![alt]()
【これからくる職業6選】注目されている理由を解説
ナレッジ
これからくるであろう6つの職業について、どんな仕事なのか、その職業がなぜ”くる”のかを解説します。具体的な仕事内容や、その職業ではどんな人材が求められているのかなどを解説します。将来に不安を抱えている人、長く安心して続けられる仕事を探している人は読んで仕事選びの参考にしてみてください。これからくる職業1.「ITエンジニア」AI時代のこれからだからこそくる職業、ニーズの高い職業として挙げられるのが「ITエンジニア」です。政府によるDX推進やクラウドサービスの普及、コロナ禍により市場が急成長したECビジネスなどにより、ITエンジニアへのニーズは急激に高まりました。ITエンジニアはもともとニーズが高く仕事が多い職業でしたが、社会の流れを見ると、今後は輪をかけて需要が高まる職業といえそうです。「これからはAIでプログラムが書けるようになって、エンジニアの仕事は減っていくかもしれない」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。しかし、ITエンジニアはプログラム(システムを動かすためのソースコード)を書くだけが仕事ではなく、システムの企画や設計もする職業です。ITエンジニアが作った設計書を見てプログラミングをする「プログラマー」の仕事はこれから減るかもしれませんが、企画力や創造力が必要なITエンジニアの仕事はむしろ増えるでしょう。AIが進化するほどITサービスでできることは増え、システムの設計をする人へのニーズも高まるからです。これからくる職業2.「Webマーケター」ニーズが安定して高い職業として「広告系の仕事」が挙げられますが、これからくる職業として特筆すべきなのが「Webマーケター」です。WebマーケターとはSNSや企業のHP、各種Web広告などを使って商品・サービス・ブランドなどのプロモーションをする職業です。企業のSNS公式アカウントやWebメディアなどを分析しながら運用し、集客や販売などの成果を高めていきます。広告系の仕事の中でもWebマーケターが「これからくる」といえるのは、インターネット広告費がテレビ広告費を上回ったこと(2019年に電通が調査)、これからの社会ではZ世代が経済の中心になっていくことなどが理由です。Z世代とは1980年~1990年代中ごろまでに生まれた世代で、物心ついた頃からデジタルやインターネットがあった世代です。テレビではなくYouTubeを、新聞ではなくネット記事やSNSを見る彼らが経済の中心となるこれからの社会では、テレビ系よりもWeb系のマーケターへのニーズが高まっていくことでしょう。これからくる職業3.「建築・土木」住宅やビルなどの建物、道路や橋をはじめとするインフラを扱う「建築・土木」の職業には安定したニーズがあります。しかし、建築・土木業界は慢性的な若手不足です。これから社会に出る若者にとって「就職しやすい」「引く手数多」という意味で、これからくる職業といえます。建築・土木関係の職業がこれからくる職業といえる理由は、それだけではありません。若手というだけで引く手数多のこの業界ですが、ITスキルが高い人材は、さらに重宝されるでしょう。建築・土木業界のもうひとつの深刻な課題が「デジタル化の遅れ」です。メールやビジネスチャットのコミュニケーション、電子書類などが当たり前の現代ですが、建築・土木業界ではいまだにFAXを使っている会社も少なくありません。ITに少し詳しいというだけでも、書類や図面、業務上のプロセスなどのデジタル化を推進できる人材として重宝されるでしょう。ベテラン世代の引退とともに失われてしまうであろう「長年の勘」をデータ・ノウハウ化したり、このノウハウを活かしたシステムを作り業務を効率化したりするためにも、高度なIT人材が求められています。たとえば画像認識やディープラーニングなどのテクノロジーを活用して道路のひび割れやわだちを見つけ、補修の緊急度を判定し、地図上に記録していくような機器・システムがあれば、業務の効率化が図れるでしょう。このような機器・システムを開発することで業務に必要な人手が減ります。慢性的な人手不足とデジタル化の遅れがあるからこそ、特にIT人材にとって、建築・土木はこれからくる職業といえるのです。これからくる職業4.「心理カウンセラー」企業に所属して働く産業カウンセラーへのニーズの増加などから、「心理カウンセラー」もこれからくる職業といえるでしょう。心理カウンセラーとは、相談者の話に深く耳を傾け、心理療法を使って彼らの悩みや不安を解決に導く職業です。高まり続ける社会的不安、便利さと引き換えに希薄になった人と人との関わりなど、これからの社会でこそ求められる職業が心理カウンセラーといえます。コロナ禍に端を発する世界的な不景気や情勢不安、核家族世帯の増加などより重くなる子育て・介護の不安と負担など、今はとにかく不安が多い時代です。これらに加え、リモートワークの普及やフリーランスの増加などにより、人と人が直接関わる機会は減る傾向にあります。個人が独立して活躍できる社会になってきたことは良いことですが、孤独を感じる人が多くなることが予想され、それに対するメンタルケアは重要性を増します。不安定で結びつきの薄い社会だからこそ、心理カウンセラーはこれからくる職業といえます。これからくる職業5.「フリーランス」これからくる職業の中でも「自由な働き方をしたいけど、安定も捨てたくない」という人におすすめなのが、「フリーランス」です。フリーランスは主に企業や個人(クライアント)からの依頼を受け、クライアントの業務を代行したり、得意とするスキルを発揮し成果物を納めたりします。わかりやすい職種では、ライター・デザイナー・エンジニア・動画クリエイターなどが挙げられます。最近はこれ以外にも営業やテレアポを代行するフリーの営業職、SNSを使って企業や商品・サービスのプロモーションをするSNS運用代行などが人気です。フリーランスはすでにある程度普及した働き方ですが、「分業の高度化」や「インターネット上のマーケティングやサービスの浸透」などにより、これから”くる”と言えるしょう。さまざまな業務をそつなくこなさないといけない会社員とは異なり、フリーランスは自分の専門スキルを高めること、専門業務をこなすことに集中できます。職場での人間関係を気にすることもほとんどないため、会社員が向いていないと感じる人でも働きやすいかもしれません。ただし、フリーランスは経理や営業も自分でしなければなりません。福利厚生や社会保険なども会社員の方が充実しています。仕事を選んだり好きな時間に働ける裁量と、会社員としての安定、どちらを取るかは慎重に考えましょう。これからくる職業6.「インフルエンサー」主にSNSからの発信を生業とする「インフルエンサー」は、これからも続くインターネット社会において、まさに「これからくる職業」といえます。その理由はZ世代の台頭やITサービスの浸透など、Webマーケターの項目でも触れたとおりです。「インフルエンサーのような人気商売は不安定で、ずっと続けられるかわからない」と感じる人も多いでしょう。たしかに、インフルエンサーになったとしても人気がずっと続くかはわかりません。ほんの少しの不用意な言動が炎上につながることもあります。自分のイメージが悪くなれば商品やサービスのプロモーションの依頼も少なくなり、「影響力はあるが稼げないインフルエンサー」になってしまうかもしれません。しかし、インフルエンサーは意外と潰しが利く職業です。たとえば企業からの依頼がなくなっても、自分のオンラインサロンやサービスを作り、人を集めて収益を得ることはできるでしょう。「どんな発信がウケるのか」「どういうキャラが、どんな層に好かれるのか」など、インフルエンサーとしての人気を高めていく中で得た知見は、マーケターとしてそのまま活用できます。自分のサービスを作ったり自分ではなく他人や企業をプロモーションしたり、インフルエンサーとしての人気と実績を活かす方法はいくらでもあります。将来性だけでなく、やりがいや適性にも目を向けようここまで紹介してきた「これからくる職業」は近い未来で”くる”と予想される職業です。世の中のニーズにかなっていれば成功する可能性は高いですが、どんな仕事でも成果を出すには努力をしなければなりません。お金を稼ぐためにはこれからくる職業を選ぶことも大切ですが、自分に合った仕事を選ぶことも忘れてはなりません。将来性だけでなく、自分自身のやりがいや適性にも目を向けて仕事を選びましょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */}
READ MORE
![alt]()
不景気、AI化など変化の早い社会でこれから求められる仕事とは
ナレッジ
機械化やAI化が進んだこれからの社会で求められるのはどんな仕事なのか、6つの職種を紹介します。いつの時代も食いっぱぐれない人、これからの時代に求められる人材になるために、たった2つ意識すべきこともお伝えします。 AI時代だからこそ活きる!これから求められるであろう仕事とは?2022年11月30日に公開されたChatGPTは世界に大きな衝撃を与えました。あまりにも目覚しいAIの進歩を人々に見せつけました。「これからの時代では、機械やAIに仕事を奪われる人が出てくる」という話題が出て久しいですが、ChatGPTはこの「機械が人間の仕事を奪う論」を加速させたといえます。しかし、機械はどこまで行っても機械、人間の指示がなければ動けません。新しい機械を生み出すのも、機能や動作を改善していくのも人間です。機械化・AI時代だからこそ輝く仕事があります。これから求められる仕事、AI時代だからこそ人間であることが活きる仕事を5つ紹介します。これから求められる仕事1.AIをブレーンにベストな提案「営業職」営業では、提案の内容がどんなに良くても「この人は何か嫌だな」と思われては買ってもらえません。反対に、商材に弱みがあっても「この人から買いたい」と、人柄で売れることもあります。AIにより営業の在り方はたしかに変わるでしょう。AIがデータを活用し、お客さま一人ひとりに合ったより良い提案を考えてくれるようになるでしょう。しかしそれをお客さまのもとに持っていくのも、その良さを伝えるのも、これからも人間の仕事であるはずです。これからの時代はAIやデータを活用して提案内容に活かせる営業職、お客さまとより深い関係が築ける営業職が求められるでしょう。これから求められる仕事2.AI時代だからこそ「エンジニア」これからはAIの進歩がさらに加速していくでしょう。これにより、プログラマーの仕事は少なくなっていくかもしれません。しかし、エンジニアはAI全盛のこれからの時代だからこそ輝く職業となるでしょう。エンジニアはどんなシステムを作るのか考え、設計図を作る人。プログラマーは設計図を見て実際にコードを書く人です。AIの進化により、「機械にコードを書かせること」はできるようになってきました。しかし、どんなシステムを作るのかを考えるのは人間の仕事のままです。エンジニアは機械と向き合う仕事に見えるかもしれませんが、実は、どこまでも人と向き合う仕事です。どんなシステムが人の悩みを解決するのか、楽しい気持ちにさせるのか、快適に使えるのか。人の心の深い部分に向き合い続けるのがエンジニアです。これからは、機械・AI全盛の時代だからこそ、人間を深く理解しシステムに反映できるエンジニアが、より求められるようになっていくでしょう。これからはIT化やDX推進のためにさまざまなシステムが必要になること、AI活用によりコードを書く時間を短縮できることなども、エンジニアがこれからも求められる大きな理由です。これから求められる仕事3.AI活用で分析精度をアップ「マーケター」マーケターもエンジニアと同じく、人の心の深い部分に向き合う仕事です。どんなデザインが、キャッチコピーが、人の心に響くのか。それを考え、人の興味や購買意欲をかき立てる仕事です。そのためには人の反応を見なければなりません。人からの反応を見て、マーケティングを改善していくために、マーケターはさまざまな分析ツールを使います。これからの時代、このようなツールの精度はより高くなっていくでしょう。だからこそ、それを使いこなせる優れたマーケターが求められます。これから求められる仕事4.AIにはない、人間ならではの知見を「コンサルタント」コンサルタントは自らの知識や経験を活かし、お客さまの課題を解決したり成功に導いたりする仕事です。マーケター同様、コンサルタントにも高い分析能力が求められます。お客さまの課題や状況、それを取り巻く市場について分析し、最適な提案ができなければなりません。そのために必要なのがAIを活用した分析ツールや、業務の効率と精度を高めるシステムです。AI全盛のこれからの時代だからこそ、人間としての思考力や知見が活きてきます。深く広い知見を持ち、AIにはできない提案ができることが、これからのコンサルタントに求められています。これから求められる仕事5.DXの遅れが深刻だからこそ「建設関連職」建設業は慢性的な人手不足と若手不足に苦しむ業界です。建設業界の平均年齢は上がり続けており、技術と知識を持ったベテランは無理が利かなくなりつつあります。彼らが引退する前に、彼らの中にある技術と知識の引継ぎをしなければなりません。しかし、それを受け継ぐ若手は足りていません。人手不足の解消はもちろん、ベテラン社員の中にある「勘」のようなものを言語化し、ノウハウとして社内に残すことが求められています。そこで役立つのが機械やAIなどのテクノロジーです。たとえば道路にあるひび割れを画像識別により見つけ、補修の緊急度を判定するようなシステムが、建設業界では開発されています。しかし、建設業界にはデジタル化の深刻な遅れがあり、このような技術の実用化はまだまだ先といわれています。他業界では当たり前のテクノロジーも、建設業界ではこれから導入されていくのです。労働人口がどんどん減っていくこれからの時代では、業界のDX推進をリードしていける、テクノロジーに精通した人材が求められています。これから求められる仕事6.人間と機械が協力してはたらく「農業」農業の世界では、すでに機械化が進んでいます。トラクターや耕運機などにより、農作業の効率は大きく上がりました。最近ではデータを管理して農機のメンテナンス時期をアナウンスしたり、ドローンで農薬・肥料の散布や作物の育ち具合を観察し分析したり、さまざまな技術が登場しています。しかし、農業のすべてが機械化されることはないでしょう。あるとしても、遠い未来の話でしょう。たとえば大根の収穫には、大根を自動で引き抜く機械が使われています。しかし、機械ですべてを収穫できるわけではなく、抜き残しは人間が収穫しなければなりません。豊富な水分と高い疲労回復力があり、部活や勉強のお供にぴったりのスイカは、畑の土の上にランダムに転がっています。一番おいしい状態でスイカを収穫するためには、大きさや「指で弾いたときの弾み方」など、人間の勘のようなものが必要です。何より農業では季節ごとに育てる作物が変わり、作業の内容も頻繁に変わります。このような雑多な作業を1台でこなせるような機械が登場するのはまだ先でしょう。作業の種類が多いため、作業ごとに機械を用意するのもコストがかかります。農業分野では機械はまだまだ人間のサポート役です。これからは機械やAIを使いこなし、農作業の効率化ができる人材が求められるでしょう。これから求められるのはどんな人材?いつの時代も食いっぱぐれない人の特徴これからの時代では、機械化やAI化が今まで以上のスピードで進んでいくでしょう。そんな中で人間にはどんな仕事が求められるのか、予測はできるかもしれませんが、確実なことは誰も言えません。しかし、いつの時代も食いっぱぐれない、どんな状況でも活躍できる人はいます。これから求められるのはどんな人材なのか。生き残るために、たった2つ意識すべきことを紹介します。主体性高く、現場に飛び込み実地で学べる人これからの時代では「主体性が高い人」こそが求められていくでしょう。自分の頭で考え、考えたことを人に話したり行動に移したりできる人です。このような人は日々の生活や仕事の中で思考力を鍛え、新たなスキルや知識を身につけていきます。彼らの学びを加速させるのが「現場での経験」です。仕事の現場に飛び込み、最先端の知見を実地で吸収できる人。お客さまがいる現場に飛び込み、そこにある課題や悩みを肌で感じられる人。このような人は圧倒的なスピードで成長します。お客さまの心の深い部分に寄り添えます。顧客が本当に求めているものを作るうえでも、お客さまからの信頼を得るうえでも、このような人材は強いです。何だかんだで「愛嬌」がある人は強い機械やAIにはない、人間だからこその強みが「愛嬌」です。愛嬌のある人は職場の先輩からもお客さまからも可愛がられます。先輩や上司からより多くのことを教えられ、いろいろな経験をさせてもらえる彼らは、人の何倍ものスピードで成長できるでしょう。お客さまに愛されていれば仕事に困ることはありません。会社から独立したり、社内向けに何か提案したりするときも、お客さまほど心強い味方はいないでしょう。AI全盛のこれからの時代だからこそ、人間であることを武器にできる人が強いのです。「この仕事なら絶対安心」はあり得ない!仕事選びよりも大切なのは、自分をブラッシュアップし続ける姿勢未来を正確に予測することは誰にもできません。この記事で紹介してきた仕事も、あくまで「これからの時代に求められそうな仕事」であり、決してなくならない絶対安心の仕事ではありません。だからこそ、たくさんのことを学び考え、人材としての自分をブラッシュアップし続ける姿勢が大切です。常に一所懸命な人は周囲から期待され、仕事の声がかかります。そこに愛嬌が加われば、ビジネスの先輩からお客さままで、たくさんの人が助けてくれるでしょう。
READ MORE
![alt]()
高校生のインターンシップとは?参加するメリットや注意点などを解説
ナレッジ
インターンシップという言葉を聞くと、大学生が就活に向けて取り組むものだと思われるかも知れません。しかし近年では、高校生向けにインターンシップを開催している企業もたくさんあります。実際に高校生がインターンシップに参加することで、たくさんのメリットを得られるのでおすすめです。そこで本記事では、高校生がインターンシップに参加する意義やメリット、注意点などをお伝えします。これから大学受験を控えている高校生の方も、インターンシップを受けることで役立つケースもあるので、ぜひ最後までご覧ください。高校生がインターンシップに参加する意味とは?まずはじめに、高校生がインターンシップに参加する意味について説明します。高校生のインターンシップとはインターンシップとは、学生が一定の期間のみ働くことを指します。一般的にインターンシップというと大学生をイメージしがちですが、高校生でも参加できるものもあります。インターンシップが可能な職場も幅広く、民間企業や公務員などで働くことができます。高校生がインターンシップに参加する目的高校生がインターンシップに参加する目的は何なのでしょうか?人それぞれ目的は異なるものの、共通して言えるのは自分の可能性を広げるために参加しているということ。実際に気になる業種や業界でインターンとして働いてみることで、本当に自分がその仕事にマッチしているのかを確かめることができます。もしくは、自分が全く知らない業界でインターンをすることで、新しくやりたいことや将来のビジョンが見えるかもしれません。今後のやりたいことや将来のビジョンが明確になることで、それに関連した仕事を選んだり、関係性のある大学選びができるようになり、結果的に自分自身の選択肢を広げることにつながります。高校生のインターンシップの内容高校生向けのインターンシップは何をするのでしょうか。もちろん企業によっても内容は異なりますが、基本的には大学生のインターンシップとさほど中身は変わりません。業種も、建設業、製造業、情報通信業、卸・小売業、飲食業、福祉業など幅広く募集しています。中には数ヶ月に及ぶ長期インターンシップもありますが、通常は期間も3〜5日程度で実施する企業が多いです。それぞれ、自分が求めている、もしくは学びたいことを教えてくれそうな企業にインターンシップに行けば問題ありません。高校生のインターンシップの概要3点高校生のインターンシップについて、概要や期間について簡単に紹介します。1.インターンシップの概要先述した通り大学生と高校生でも内容はさほど変わりません。基本的にはインターンシップを募集している民間企業や行政員などから、自分が行きたいと感じる職場に応募し、その場所で働いている人と一緒に働きます。企業側は、貴重な業務の時間を使ってインターンシップ生に仕事を教えてくれるため、インターンシップ生側は企業に感謝と敬意の気持ちを持って働くことが大切です。2.インターンシップの募集時期高校生向けのインターンシップの求人は、参加しやすいように春休みや夏休みにかけて行われることがほとんどです。そのため、春休みや夏休みが始まる1ヶ月ほど前から募集が開始される傾向にあります。高校生向けのインターンシップに参加を検討している方はぜひ、その時期になったら忘れずに気になる業界のインターンシップ情報を探してみてください。3.インターンシップ期間中は賃金が発生しないほとんどの場合、インターンシップは基本的に賃金が発生しません。そして高校生向けに開催されるインターンシップの多くは、高校と企業側が提携し、授業や社会経験の一環として実施されます。ボランティアとしての参加ではあるものの、しっかりと仕事をするという意識を持ち、かつ自分自身の社会経験を積む場だと思って参加するようにしましょう。高校生がインターンシップに参加するメリット3つ最後に、高校生がインターンシップに参加するメリットについて説明します。メリットは大きく分けて次の3つです。1.高校卒業後の進路選択の幅が広がる高校生がインターンシップに参加することで、高校卒業後の進路選択の幅が広がります。実際にインターンシップを通じてさまざまな業務を経験し、働いてみることで自分にその業界が向いているのかどうかが分かります。例えばスポーツ系企業のインターンシップに参加することで、自分にはスポーツ業界が向いているのかどうか判断する大きな材料となるのです。まずはなんとなくでもいいので、自分がやりたいことや志望する業界の会社でインターンシップを募集しているかチェックし、もし募集していたら実際に応募してみることをおすすめします。2.実際に「働く」を体験できる実際にインターンシップを通じて「働く」とはどういうことなのかを肌を持って感じられます。インターンシップは基本的にそこで働いている社員さんと同じように出勤して、業務をこなします。高校生のうちから、社会に出て実際に働く経験ができるのは、今後の人生にとって大きな財産となるでしょう。3.社会人のマナーが身につく実際にインターンシップとして企業で働くことで、社会人のマナーを身につけることができます。基本的な立ち振る舞いに加え、お客様への対応や言葉遣いなど、普段の学校生活やアルバイトではなかなか身につけられないような、社会人としての基本的なマナーを学ぶことができます。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 高校生がインターンシップに参加する際の注意点3つたくさんの学びが得られる高校生のインターンシップですが、参加するにあたって気を付けなければならないこともあります。インターンシップ参加時に注意すべきことは、以下の3点です。自ら笑顔で挨拶する当然のことですが、インターンシップ先では率先して自ら積極的に笑顔で挨拶するようにしましょう。自ら積極的に挨拶することで、インターンシップ先の方々とより良い関係性を築きやすいのはもちろん、お互い心地よくインターンシップ期間を過ごすことができます。積極的に行動するインターンシップ先では自ら積極的に行動しましょう。与えられた仕事に一生懸命取り組むことに加え、それ以外の仕事も自ら進んで積極的に取り組むことで、周りからより良い評価が得られます。また、主体的に動くことで新たな気付きや学びを得られ、より成長し、充実した時間を過ごせます。分からないことはどんどん質問するインターンシップ先で分からないことがあったら、迷わずにどんどん積極的に質問してみましょう。分からないことをそのままにしていると、逆に周りに迷惑をかけてしまいます。なにか疑問や質問があれば、タイミングを見てすぐに聞くようにしましょう。参考:長期インターン・有給インターン求人を探すなら「ココシロインターン」参考:スタディチェーン高校生は積極的にインターンシップに参加してみよう高校生がインターンシップに参加する意義やメリット、注意点について解説しました。高校生がインターンシップに参加することで、社会経験になるのはもちろん、礼儀正しい言葉遣いや社会人としてのマナーが身につくなど、たくさんの良いことがあります。積極的に学ぶ姿勢を持ってインターンシップに参加することで、自身の成長も見込めるので、参加しようか迷っている方は、まずは気になる企業や業界でインターンシップを募集しているかどうか、調べてみてはいかがでしょうか。
READ MORE
![alt]()
職業体験を控える中学生必見!人気の職場や体験内容を解説
ナレッジ
「職業体験で中学生が体験できる職業の種類が知りたい」中学生生活でのビッグイベントの一つ、職業体験。本記事では、そんな職業体験で人気な職業を含む10種の職業について解説しています。職業体験自体の概要や、何ができるかについても解説しているので、職業体験を控えている中学生の方は、ぜひお読みください。 職業体験とは職業体験とは、一般的に「学生や求職者が実際の現場で働くこと」を指します。現場における業務内容や雰囲気、職場のルールやコミュニケーション方法などを実際に体験し、職業や職場、ひいては社会を勉強する意味合いが強く、労働対価としての賃金は基本的に発生しません。なお、金銭報酬が貰える場合は「体験入店」や「インターンシップ」に該当します。また、職業体験を通じて自分が興味を持っている職種と実際の現場のギャップを知り、職業選択に役立てられる点も職業体験の意義の一つです。ただし、学校で実施する職業体験先が楽しいと思えるかどうかは人によります。日本では大多数の人は会社員になるので「こんな仕事もある」くらいの認識で捉えた方がいいでしょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 職業体験で中学生に人気の職業5選次に、中学生の職業体験で人気の職業を5つ、紹介します。 幼稚園警察農家図書館鉄道関係 それぞれ、職業の特徴や体験内容について解説していきます。 職業1.幼稚園幼稚園は、子どもたちが遊びながら学び、成長するための場所です。保育者は、子どもたちを見守りながら、ともに遊んだり歌ったり話を聞いたりして、楽しく過ごすことが求められます。職業体験では、幼稚園での子どもたちとの交流が体験できます。たとえば、園内の見学や、保育者の先生について保育の補助をするなど。ときには、子どもたち同士のトラブルを仲裁することもあるでしょう。こうした体験を通して、幼稚園で働く魅力や、子どもたちの成長を支える大変さを実感できます。 職業2.警察警察は、法を守り、治安を守る役割を持つ職業です。警察官は巡回や取り締まり、事件の捜査や新たな犯罪の予防などを行い、地域の安全を守っています。警察官になるには、さまざまな訓練や試験を受ける必要があります。職業体験では、警察官が行っている業務に触れたり、装備や車両などを見学したりすることができます。警察官として働くことは、責任やストレスが大きい一方で、地域の安全を守り、社会貢献できるやりがいもあります。実際の警察署内では、その独特の緊張感も感じられるでしょう。 職業3.農家農家は、農業を営む職業のことです。野菜や果物、米などを栽培し、牛や豚、鶏などを飼育します。農家の仕事には、農作業や畜産業務、農産物の受け渡しや販売、農業機械の整備や修理などがあります。体験内容としては、野菜や果物の収穫や、牛や豚などの動物の餌やり、飼育など。また、農家によっては、自然観察や散策、食事体験などを提供している場合もあります。農家の仕事には体力を使うことも多く、天候や季節による忙しさもあるため、責任感や労働意欲、忍耐力が求められます。 職業4.図書館図書館は、本や雑誌、DVDなどのメディアを収蔵し、貸し出しや閲覧を提供する施設です。図書館司書は、利用者の案内や質問への対応を行ったり、貸し出し業務や受け取り業務、蔵書の整理や保管、展示企画の立案や実施などを行ったりします。図書館での職業体験では、利用者の案内や貸し出し業務、書架の整理や本の回収作業などが行われます。図書館は、本や知識に触れる場所としてだけでなく、コミュニティースペースとしても機能していることが多く、地域の文化的交流の実情も見られるかもしれません。 職業5.鉄道関係「鉄道関係」には、列車や駅などの運営やメンテナンス、旅客サービスを提供する仕事が含まれます。鉄道関係の仕事に就く人たちは、列車の運行管理や運転、車両の点検や修理、駅務員や車掌として乗客に接客し案内するなどの業務に従事します。体験内容としては、鉄道車両・駅の設備見学や運行の状況確認、列車の運行操作シミュレーション、車両内での運賃精算や車内アナウンスの体験、車掌業務での乗客対応などがあります。鉄道に携わる職業では、安全性や時間厳守が求められるため、正確性や責任感、集中持続力などが求められます。 職業体験で中学生がほかに体験できる職業の種類5選ここまで、人気な職業5種を紹介してきましたが、ここからは多くの中学校で体験先になっている職業を同じく5つ紹介していきます。 薬局病院飲食店ホテルコンビニ それぞれ、職業の特徴と体験内容を見ていきましょう。 職業1.薬局薬局は、医薬品の販売や処方箋の調剤、健康相談などを行う施設です。薬局体験では、薬剤師や薬局スタッフと一緒に、お薬の種類や使い方、健康管理の方法を学ぶことができます。また、薬の発注や在庫管理、医師や病院との連携など、薬局の仕事に携わる様子も知ることができる薬局も多くあります。 職業2.病院病院は、医療サービスを提供する施設です。患者の病状を診察し、治療や手術、看護、リハビリテーションなどを行っています。病院には、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、作業療法士、理学療法士など、多くの職種があります。職業体験では、病院内の職員のアシストや業務の見学などができる場合が多く、患者に対するコミュニケーションや、医療に必要な知識や技術を学べるところもあります。ただし、病院は感染症対策などで厳しいルールがあるため、ほかの職場ほど自由度は高くありません。 職業3.飲食店飲食店とは、お店で提供される食事やドリンクなどのサービスを扱う職業です。店員として、接客や注文・調理、清掃などの業務を担当する人や、店長として店舗全体の運営やマネジメントを行う人がいます。職場によっては、厨房を中心に調理に携わる仕事もあります。中学生の職業体験では、接客やレジ、食器洗浄、片付け、配膳などを通じて、飲食店での仕事の様子やカスタマーサービスの意義を学ぶことができます。 職業4.ホテルホテルでは、宿泊施設として客室や宴会場などを提供し、観光客やビジネスマン、地域住民などに対し、サービスを提供します。フロント、客室清掃、レストラン、マーケティングなどの職種があり、英語が必要な場合もあります。中学生の体験内容としては、キッチンでの食材調理、客室の清掃、ベッドメイキングなどが挙げられます。また、ホテル内の施設や設備の案内を担当するフロント業務に参加できる場合もあります。 職業5.コンビニコンビニは、24時間営業で、日用品、食料品、お菓子、飲み物、アルコールなどを販売する小売店です。体験内容としては、清掃、レジ業務、商品の陳列、補充、注文、接客などが挙げられます。陳列・補充のスピード感、それらの丁寧さ、コミュニケーションの大切さなど、社会人になってからも活用できることを多く学べるでしょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 職業体験は将来の選択の種職業体験は将来の選択の種になります。実際に仕事を経験することで、自分に合った職種や業界を見つけることができ、進路選択や就職活動において大きなアドバンテージになるでしょう。また、職業体験を通じて、社会人としてのマナーやコミュニケーション能力、職場での仕事の進め方など、社会人としての基礎的なスキルを身につけることもできます。決して、職業体験をした職業を目指す必要はありません。興味がなければこれをきっかけに様々な業界の仕事をしている大人の話を聞きにいくのがいいでしょう。自分の興味をもつ職業が見つかるかもしれません。
READ MORE
![alt]()
高校生の進路の決め方は?手順や大切なことについて解説
ナレッジ
本記事では、高校生の進路の決め方、手順、進路を決めるうえで大切なことについて詳しく解説しています。大人と子どもの「はざま」にいる高校生、将来を思い悩む人も少なくないでしょう。高校生卒業者の進路割合についても解説しているので、進路に悩む高校生の方は、ぜひお読みください。「高校生が進路を決めるうえで大切なことは?」「高校生の進路の決め方や決める時期は?」「高校生卒業者の進路割合を知りたい」大人と子どものはざまとも言われる高校生、将来を思い悩む人も少なくないでしょう。本記事では、高校生が進路を決める手順から大切なポイントまで、詳しく解説していきます。進路に悩む高校生の方は、ぜひ最後までお読みください。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 高校生が進路を決めるうえで大切なこと5つまずは、高校生が進路を決めるうえで大切なポイントを紹介していきます。主なポイントは以下の5つです。 進学候補先へ実際に行く学部や教授をしっかり調べるなりたい職業がある場合は逆算して進路を考える合格の目処はあるか自分が納得できているか どれも忘れがちですが、大切なポイントです。 進学候補先へ実際に行く実際に足を運んで学校を見学することで、授業や施設、生活環境などを直接確認できるため、自分に合った学校を見つけられます。設備が乏しかったり、学舎が汚かったり、敷地が狭ければ、授業や生活に支障をきたすかもしれません。パンフレットや公式HPで満足せず、実際に行って学校内を見て回り、求めている環境が実際そこにあるのかを確認しましょう。 学部や教授をしっかり調べる同じ名前の学部でも、大学によっては内容が異なる場合があるため、大学ごとに学部をしっかり調べる必要があります。たとえば、同じ「心理学部」でも、医療や福祉の現場で活躍する「臨床心理学」と、人間社会の傾向や個人間のコミュニケーションに関する「社会心理学」では、学ぶ内容が大きく変わってきます。また、教授によって得意分野や実際に研究できる分野も異なります。同じ心理学部の例で言えば、犯罪心理学に精通している教授が在籍していない大学も珍しくありません。学部だけでなく、教授についてもしっかりと調査しておきましょう。 なりたい職業がある場合は逆算して進路を考えるここでの「逆算」とは、目標とする職業に必要なスキルや知識、資格などを具体的に洗い出し、それを達成するために必要な進路や取るべきアクションを決定することです。たとえば、国語の高校教諭になりたい場合は、教育学部の国語教育専攻か、文学部の国文科専攻を選択するのが一般的です。入学後も、教職課程を履修する必要など、通るべきポイントがいくつかあります。そのポイントを逃さないよう、逆算して進路を決定しましょう。 合格の目処はあるかここでの「合格の目処」とは、単純に偏差値が足りているかというだけでなく、最適な受験方法や受験制度を選択できているか否かも含まれます。たとえば、学力や志望校レベルに不安がある場合でも、得意科目のみで受験できる制度や推薦制度を利用することで、合格にグッと近づくかもしれません。また、滑り止めの学校もしっかりと検討し、万が一の場合に備えることも意識して進路選択を行うことも大切です。 自分が納得できているか進路選択に限らず、人生におけるすべての選択は、常に後悔する可能性をはらんでいます。しかし、選んだ瞬間に自分が納得できていれば、それが将来の自分の納得材料になります。「なんとなく」ではなく、自分が納得するためにも根拠を持って進路選択を進めていきましょう。 高校生で進路が決まらない場合はどうすればいい?進路の決め方の手順ここからは、実際に進路を決める手順を紹介します。大まかに分けると、以下の3ステップが基本です。 自己分析を行う就職か進学かそれ以外かを決める目的に応じて進路を決める それぞれ順に見ていきましょう。 手順1.自己分析を行うはじめに自己分析を行うことは進路選択において非常に重要なステップです。進路が決まらないという方は、このステップを飛ばしている可能性があります。自分自身の長所や短所、やりたいこと、得意を明確にすることで、適職や進学先を絞っていきましょう。自己分析の方法としては、自己探求のワークショップやキャリアカウンセリング、職業診断テストなどがあります。それぞれの手法を活用し、自分自身を客観的に見つめ直すことが重要です。自分で見つけられない時は大人に相談することも大切です。家族や先生以外の大人に相談することもあらたな自分を発見するのに有効でしょう。 手順2.就職か進学かそれ以外かを決める自己分析を経て自身の興味や長所・短所がわかったところで「就職か進学かそれ以外か」を決めていきましょう。このステップでは、自己分析を活用して、なりたい職業ややりたいことを具体化します。なりたい職業に就くためには進学が必要な場合もあれば、実力を磨くために就職し、その後転職する方向性もあります。人生は長いので回り道しながら選択していく方法もありです。 手順3.目的に応じて進路を決める最後は、目的に応じて具体的な進路先を絞っていきます。ここでは、以下の2パターンに分けて深掘りします。 就職進学 それぞれ自分に合った方を確認してください。 就職の場合就職を選択した場合の考え方は、基本的に「なりたい職に就く」か「やりたい仕事へつながる職に就く」の2通りです。後者の場合、自分の希望する職種を明確にし、その職種に必要なスキルや知識を身につけるために、適切な就職先を選びましょう。また、入社後にも上司や先輩からの学びは絶えません。将来的にも、希望する職種に就くために必要な経験を積んでいくことが大切です。「勉強が苦手」という消極的な理由で選択しないよう注意しましょう。 進学の場合進学する場合、将来何をしたいかを明確にし、その目的にあった進学先を選ぶことがもっとも望ましい決め方です。たとえば、医療系の仕事に興味がある場合は、医療系の大学や専門学校をリサーチして、カリキュラムや実習内容、就職実績、教員の経験などを比較検討して決めましょう。ただし、大学在学中に新しくやりたいことが見つかることも少なくなく、その道もまた素晴らしい選択です。将来何をしたいかを明確にできない場合でも、不安がる必要はありません。このステップが進路選択にもっとも大きな影響を与えるため、十分な時間と精神的余裕を持って進学先を決めるようにしましょう。 高校生が進路を決める最適な時期高校生が進路を決める時期は、一般的に高校2〜3年生の頃です。早ければ2年生の頃から自己分析を行い、就職や進学など各々の進路選択のために必要な情報を得る人が一定数います。1年生のうちから活動すれば周りと差をつけられるでしょう。残りの人は、高校3年生の春・夏ごろから行われる入試説明会やオープンキャンパスなどの結果を踏まえ、進路を選択します。ただし、遅すぎて困ることはあっても、早すぎて困ることはありません。難関大学であるほど合格する人は早いうちから活動しています。この記事を読んでいる今日、できることから始めていきましょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 高校生卒業者の進路割合最後に、高校生卒業者の進路割合を見ていきます。令和元年度の高校卒業者の進路を見ると、88.7%の人が以下の3つのいずれかの進路に進んでいます。 大学・短期大学進学専門学校進学就職 ここからは、それぞれの割合と特徴を解説していきます。 大学・短期大学進学令和元年度の大学・短期大学進学率は54.8%です。大学・短期大学進学は高校生卒業者の主要な進路の一つで、高度な専門知識・技術を4年で身につけられる4年制大学、短期間で幅広い知識を身につけ、専門的な技能が学べる短期大学などがあります。大学や短期大学卒業後には、各分野で幅広いキャリアチャンスがあります。 専門学校進学令和元年度の専門学校進学率は16.3%です。専門学校進学は、主に実学に特化した教育を受け、就職に必要な技術を短期間で身につけるために選ばれる進路です。美容系やIT・Web、福祉、ビジネスなど、専門分野・職種ごとに学ぶことができ、専門知識を身につけることで即戦力として活躍できます。 就職令和元年度の就職率は17.6%です。高校生卒業者の進路の一つである就職は、社会で働きながら、経験を積み、技術やスキルを身につけることができます。就職先として、大手企業や中小企業、さらには公務員、各種専門職などがあります。 高校生の進路決定はリサーチが命自分が持つ能力や興味に合った進路を見つけるためには、周囲の人の意見や、進路に関する情報を収集する必要があります。情報が豊富にあるなかで、正しい判断をするためにも、さまざまな角度からリサーチしましょう。大人と話す機会を増やすことで人生のモデルが見つかることもあるかもしれません。積極的に課外活動をすることをお勧めします。
READ MORE
RePlayce, Inc. ©2025. All Rights Reserved