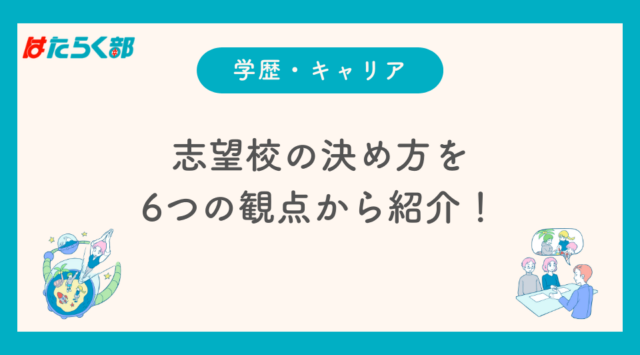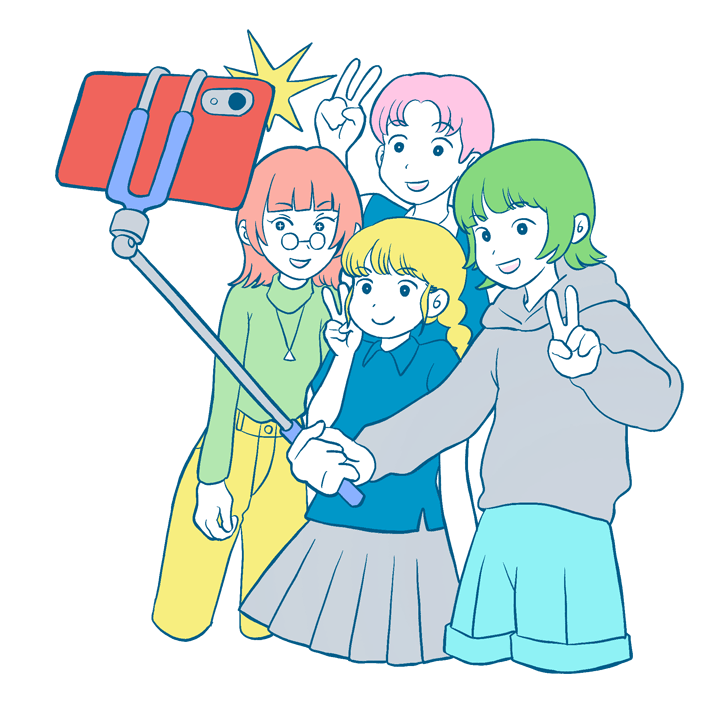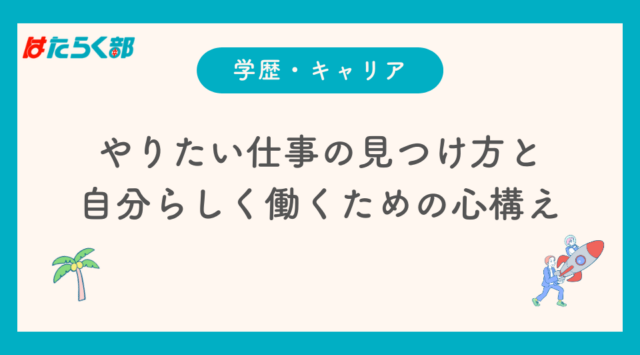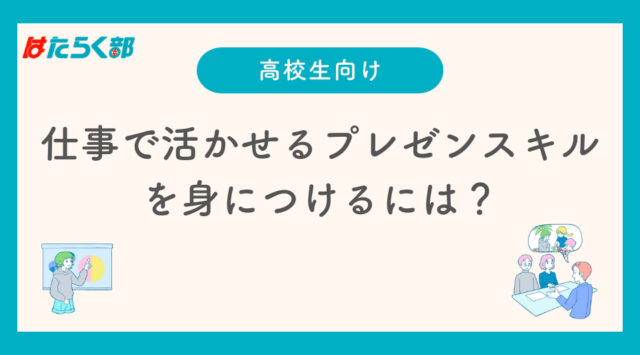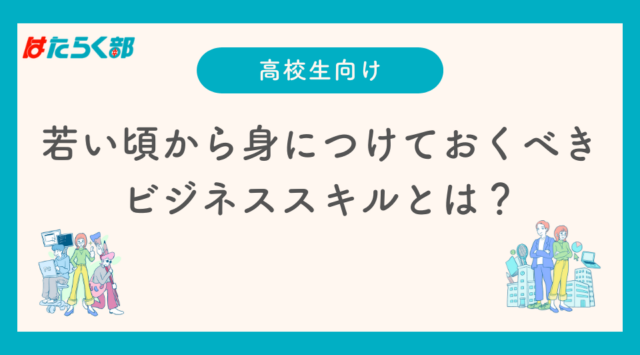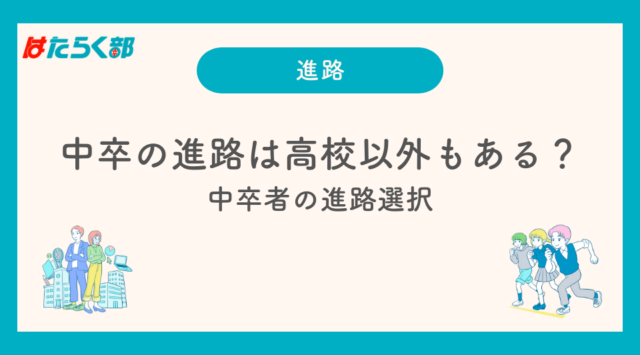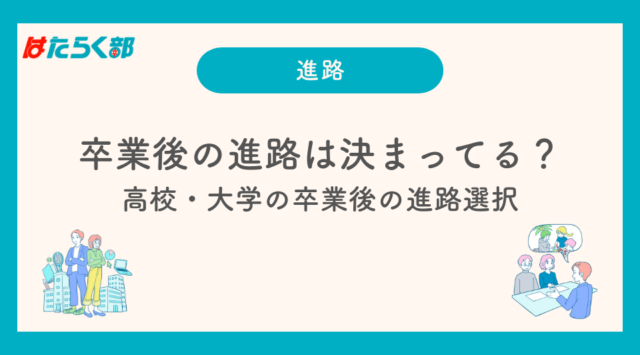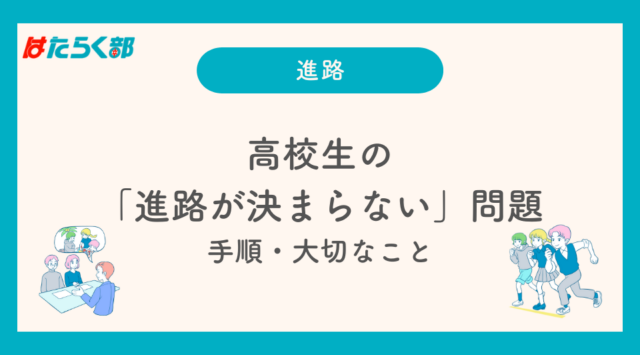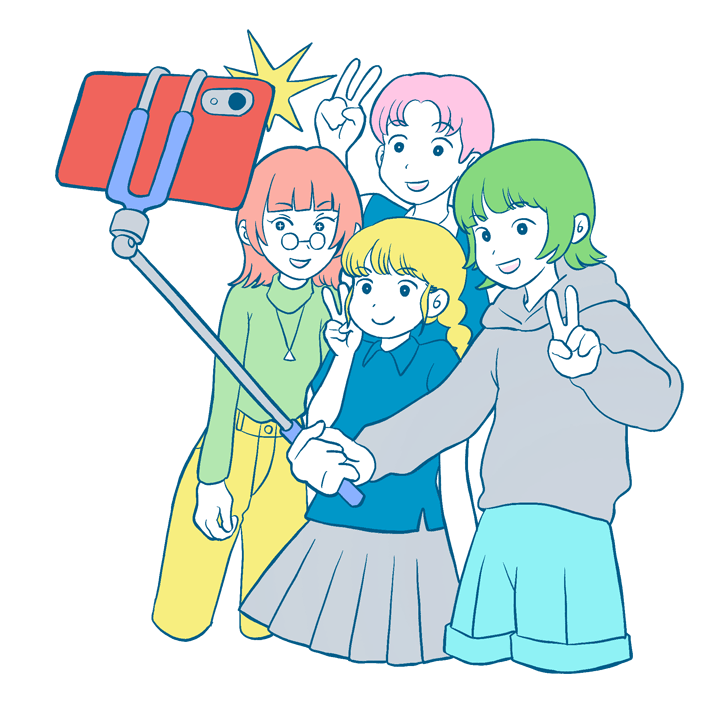
Blog
![alt]()
志望校の決め方を6つの観点から紹介!受験計画にも役立てよう
ナレッジ
中学生や高校生にとって重要な志望校決めは、誰もが悩む大きな壁です。志望校を決める際には大きく6つの観点から決める方法があります。反対に失敗してしまう決め方もあり、後悔しない選択をするには注意が必要です。また、中学生と高校生によって受験スケジュールが異なります。志望校を決めるために必要な情報収集の手段、志望校が決まった後の流れまで紹介します。学校生活において大きな選択となる志望校選びは、沢山の人がぶつかる壁です。この記事では志望校の決め方と、失敗してしまう決め方まで説明していきます。後悔の無い志望校選びをしましょう。 志望校はいつまでに決めるべきか志望校の最終決定は、中学生と高校生で時期が異なります。中学生の場合中学3年生になると12月頃に三者面談が実施され、そのころには最終的に決まることになります。夏のオープンスクールで情報を集め、秋頃には大体の志望校を決めておきましょう。また、公立入試は2月上旬から始まるのに対して、私立入試は1月上旬から始まります。受ける高校によっても変わることに注意しましょう。高校生の場合高校生が志望校を決めるおすすめの時期は高校2年生です。大学受験は出題範囲が広く、受験対策をするための時間をしっかり確保できるかどうかが、合格の分かれ道となります。また、高校受験と異なり大学や試験内容によっても対策方法が異なるため、高校2年生から受験勉強を計画的に始められるよう、早めに志望校を決定することをおすすめします。 志望校の決め方・6つの観点志望校は、大きく分けて6つの観点から絞る事ができます。1.自分の夢ややりたいこと将来の夢ややりたいことがはっきりと決まっている人は、自分の想いを軸に志望校を決めましょう。例えば、学校の先生になりたい場合は教育学部を目指すという進路選択になります。具体的な夢が決まっていない場合でも、やってみたいことや興味があることから掘り下げてみましょう。2.勉強する内容将来の夢が明確でない場合、学校でどんな勉強をするのかという観点から決める方法もあります。例えば、商業高校や農業高校、工業高校など普通科目以外の教科を学べる学校を調べたり、興味がある授業を調べたりすることで、希望の高校・大学を見つけられる可能性があります。3.大学進学実績や就職実績大学進学を目指す人や、なりたい職業が決まっている人は、進学実績と就職実績から志望校を絞る決め方もあります。卒業したその先の実績がしっかりある学校は、自分の希望する進路を歩める確率が上がります。それぞれ学校のパンフレットやホームページに掲載されているため、情報収集しておきましょう。4.自分の実力と学校の偏差値将来の夢やなりたい職業は具体的にないが、進学はしておきたいと考えている場合、自分の実力や学校の偏差値から志望校を絞る決め方もあります。自分の偏差値からはほど遠い学校を受けても受験に失敗してしまい、勉強のモチベーションを下げてしまう可能性もあります。無理せず自分のペースで学び続けることは決して悪いことではありません。5.学校の場所や学費通う場所・学費の制約条件がある場合は、それを基準に志望校を絞る決め方もあります。自宅から通うことが先に決まっていれば、県内の自宅から近い学校で比較していきます。できるだけ学費を抑えたいという場合は国公立を選ぶなど、大きな判断基準となります。6.学校の校風理想の学校生活がある場合は、学校の校風から志望校を絞る決め方もあります。学校によっては、自由な校則・文武両道・規律が厳しいなど特徴が異なります。自分が過ごしたい学校生活をイメージし、それに近い校風の学校を選ぶことは、学校生活の充実度につながります。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 失敗してしまう決め方4選これまで志望校の決め方を紹介してきましたが、以下の方法で決めてしまうと後悔する学校選択になってしまう可能性があります。1.知名度・イメージだけで決める学校の知名度やイメージだけで志望校を絞る決め方は、実際に入学したときや過ごしていく中でマイナスのギャップを感じる場合があります。また、自分の性格や実力に合っていなかったり、ストレスになってしまう要因が含まれることもあります。2.学校や塾の先生に勧められたから先生は真摯に相談にのってくれたり、自分の成績や学校生活の態度も知ってくれているため、自分に合った学校をおすすめしてくれるかもしれません。しかし、先生に進められるがままに進学した結果、本来は行きたい学校ではなかったと後々公開したとしても、最終決定の責任は自分にあります。先生の意見は参考程度に、大事な志望校の選択は自分自身で決めましょう。3.友達と一緒の学校だから仲のいい友達と一緒の学校に行きたいから、という理由で志望校を絞る決め方は良い方法ではありません。友達と自分の進路や将来のキャリアの進み方は全く別物です。自分自身と向き合い、志望校を決定することが一番です。4.偏差値だけで決める志望校の決め方で、自分の実力や学校の偏差値から決める方法を紹介しました。しかし、偏差値だけで志望校を絞る決め方は良い方法ではありません。どんな勉強ができるのか、将来どんな職業につけるのかは、学校や学科によっても大きく異なります。自分の実力で行ける学校を絞った後は、本当にその学校で学びたいのか、不安な点や譲れない条件は他にないのか深く考えましょう。情報収集の方法学校を決めるための情報収集の方法は沢山あります。オープンキャンパス・オープンスクールに行ってみる実際に学校に足を運ぶことができる、オープンキャンパスやオープンスクールをぜひ活用しましょう。学校の模擬授業を体験できたり、学校の生徒・学生と話せる機会もあります。学校の校舎や部活動の雰囲気などを目で見て、学校生活を体感してみてください。学校の先輩や先生、身近な社会人の話を聞く自分より知識が豊富な先輩や先生、身近な社会人の方に聞いてみると、ネットには掲載されていない情報が手に入ります。周りの人がどんな学校生活を過ごし、もし自分がもう一度、生徒・学生に戻れるならどんな志望校選びをするのか聞いてみましょう。学校の進路資料室沢山の情報を一度に収集できるのは学校にある進路資料室です。進路に関わる資料や学校のパンフレットが沢山集まっています。受験対策本が置いてある場合や、先輩の受験体験談などレポートがある学校もあります。自分が在籍する学校の進路資料室を最大限活用して、志望校選びの重要な情報収集源にしましょう。 志望校が決まったらすること志望校が決まった後は、どんなことから手を付けていけばいいのでしょうか。受験の計画をするまずは、入試までの受験計画を立てましょう。苦手分野を克服するための学習プランや模試を受ける時の目標設定などがあるとモチベーションを維持しながら勉強ができます。勉強の手段を決める受験計画が立てられたら、勉強の手段を決定します。勉強の手段は、独学・家庭教師・塾の3つになります。時間や予算が関わってきますが、自分にとってより効率的で効果的な勉強方法を選びましょう。勉強する受験計画を立てられ、勉強の手段が決まればあとは勉強するのみです。繰り返し問題を解き、苦手分野を克服していきましょう。勉強計画は途中から変更することもできますし、友達と助け合いながら勉強を進めていくことも重要です。課外活動をする総合型選抜や推薦を活用して大学進学を考える場合は、課外活動をしていると有利になります。積極的に課外活動をしましょう。早いうちから周りの人と差をつける行動や実績を積むことでコミュニケーション能力や企画力、プレゼンテーション能力を高めることができ、受験時に役に立つでしょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 早い段階で計画的に志望校を絞っていこう志望校の決め方のポイントと、その後の取り組みまで紹介していきました。受験を経験した人が口をそろえて話すことは、もっと早くから取り組めばよかったということです。ペースは人それぞれですが、早いに越したことはありません。志望校選びに手を付けられていない人も、まだ決め切れていない人も計画的に志望校を絞っていき、後悔のない選択をしましょう。
READ MORE
![alt]()
やりたい仕事の見つけ方と自分らしく働くための心構え
ナレッジ
中高生のみなさんは、やりたい仕事はみつかっていますか。この記事ではやりたい仕事が見つからないという中高生向けに、やりたい仕事の見つけ方や、やりたい仕事がどうしても見つからないときにできることをお伝えします。本記事を読めば、やりたい仕事を見つけて、自分らしく働くための心構えが身につくはずです。やりたい仕事が見つからない原因やりたい仕事が見つからないよくある4つの原因を紹介します。自分に当てはまるものがないか確認してみましょう。どんな仕事があるのか、情報不足になっているやりたい仕事を見つけるためには、まずはどんな仕事があるのかを知らなくてはなりません。どんな職業があるのかを知ったうえで、その中から自分に合っていそうなもの、やりたいと感じる仕事を探してみましょう。自分について理解できていない自分がどんなことにやりがいを感じるのか、どんなことが得意なのか、自分について理解できていないことも、やりたい仕事が見つからない原因です。普段の生活や過去を振り返ってみて、一生懸命に取り組めたことや、好きだと感じたことを振り返ってみましょう。自分の価値観や将来と向き合えていない自分の価値観と向き合えていないことも、やりたい仕事が見つからない原因です。保護者からのアドバイスを受け入れることも大切ですが、自分のやりたい仕事と「親が自分にやってほしいと思っている仕事」が違うこともあるでしょう。保護者と意見が合わなかったりアドバイスを受け入れられないと感じるなら、家族以外の大人に相談するのがいいかもしれません。また、たとえば親が「いい大学に進学して、大企業に就職することが大切」という考えだったとしても、「高校を卒業したらすぐに就職して、早く働きたい」「職人系の仕事について、とにかく腕を磨いていきたい」という人もいるでしょう。進学したり、安定した仕事に就くことが必ずしも正解とは限りません。まずは自分がどんな仕事をしたいか、仕事に何を求めているのかを考えて、保護者や先生だけでなく、様々な大人に相談してみましょう。やりたい仕事の見つけ方ここからは、やりたい仕事の見つけ方を4つ紹介します。どれもすぐにできることなので、上から順番に試していきましょう。まずは自分にとって大事なことをハッキリさせるやりたい仕事を見つけようとする前に、まずは自分が仕事に何を求めているのかを明確にしましょう。給料が多ければ残業や休日出勤が多くても構わないという人もいれば、毎日定時に帰れること、カレンダー通りに休めることが第一という人もいます。「やっていて楽しい」「社会の役に立つ」などのやりがいで仕事を選びたいという人も多いでしょう。自分にとって大事なことをハッキリさせれば、やりたい仕事や向いている仕事も見えてきます。これまでの学生生活について振り返る自分が仕事に何を求めているのかわからないという人もいるでしょう。そんなときは、これまでの学生生活やアルバイトなどを振り返ってみてください。自分は何をしているとき、人からどんなことを言われたときに充実感を得ていたのかを思い出すのです。たとえば人から感謝されるのが何よりやりがいにつながる、という人には、人の困りごとを解決してあげる仕事が向いているでしょう。営業や接客職、看護などお客様に直接対応する仕事が向いてるかもしれません。他にも「細かい作業が好きだから機械系の仕事に就く」「数字を扱うのが得意だからデータ分析の仕事がしたい」など、やりたい仕事の見つけ方は人それぞれです。アルバイトで感じた不満や将来に対する不安を書き出してみるやりたいことではなく、やりたくないことを軸に仕事を探す方法もあります。アルバイトをしていて感じた不満や、将来に対する不安を書き出してみて、それを解決できそうな仕事を探してみましょう。たとえばコンビニのアルバイトをしていて「品出しは好きだけど接客は苦手」と感じているなら、お客さまと直接関わることのない仕事を探すといいかもしれません。将来に対する不安がお金に関するものなら給料が高い仕事や安定した仕事、大企業への就職を目指すといいでしょう。「楽しくない仕事に就いて、長く続けられなかったらどうしよう」と思うなら、やっていて楽しいことや好きなことを軸に仕事を探すのもおすすめです。適職診断を受けてみるやりたい仕事を自分で見つけられないなら、適職診断を受けてみるのもいいでしょう。自分では気づいていない自分の性格や能力を教えてくれたり、それを踏まえた適職をピックアップしてくれたりします。診断で出てきた仕事の中にやりたい仕事がなくても、「やってみたら意外と向いていた」ということもあるかもしれません。 やりたい仕事がどうしても見つからないときは?やりたい仕事がどうしても見つからないときに試したい3つのことを紹介します。これらの方法を試していくうちにやりたい仕事が見つかることもあれば、見つからなくとも仕事や生活に対する不満が解消されることもあるでしょう。やりがいではなく条件で仕事を選んでみる仕事においてやりがいはとても大切ですが、それだけだと後悔するケースもあります。社会に出ると自分が稼いだお金で生活をしていくことを考えると、給料や福利厚生などの条件も重要になります。仕事選びをする際に、条件面が合っていないと長く続けられない、という側面もあるため、条件面に目を向けると、意外と自分自身が大切にしているものが何か、も見えてくることがあります。やりたい仕事はひとまず諦め、「向いてる仕事」を探してみるやりたい仕事が見つからないなら、ひとまず諦め、まずは「向いてる仕事」を探してみるのもいいでしょう。向いている仕事といっても、特別なスキルや才能を探す必要はありません。「人と話すのが好きだから、接客や営業の仕事に向いてるかも」「細かい作業が得意だから、工場の仕事ならできる」くらいで構いません。向いていることやできることは、やっていて苦にならないでしょう。もしも今の仕事が向いておらず、それで溜まった不満からやりたい仕事探しをしていた場合、向いている仕事に転職するだけで満足できることもあります。「自分の才能や適性をもっと活かしたい」という気持ちから、向いている仕事がやりたい仕事へと変わっていくこともあるでしょう。誰もがうらやむ理想の仕事よりも、自分らしい働き方・生き方に目を向けようやりたい仕事の見つけ方は人それぞれです。深い自己分析を通してやりたい仕事を見つける人もいれば、何となく選んだ仕事が楽しくて、いつの間にか「これが自分のやりたい仕事だったんだ」と思えるようになる人もいます。自分らしい働き方や生き方に目を向ける方と、やりたい仕事は見つかりやすくなります。「給料が高くて毎日決まった時間に帰れて、世間体も良くて仕事内容も面白い仕事」などそうそうありません。何を面白いと感じるかは人それぞれだからです。まずは自分が仕事に何を求めているのかを考え、それを満たせる「適職」を探してみましょう。
READ MORE
![alt]()
【高校生必見】仕事で活かせるプレゼンスキルを身につけるには?
ナレッジ
高校・大学生活を送っていると、あるテーマについて資料を作って発表するプレゼンテーションの機会も少なくありません。そこで必要となってくるのが、大勢の人の前で上手く発表するプレゼンスキルです。プレゼンスキルは社会人になってからも求められる場面が多いため、高校生や大学生のうちに身につけておくと将来とても役立ちます。本記事では、高校生のうちから将来仕事で活かせるプレゼンスキルの習得方法や、プレゼンスキルを上達させるためのステップについて解説します。プレゼンスキルを伸ばしたい方は必見の内容となっているので、ぜひ最後までお読みください。プレゼンスキルが重要な理由3つなぜプレゼンテーションスキルが重要なのでしょうか?主な理由は大きく3つあります。1.ビジネスにおいて欠かせないからプレゼンスキルはビジネスにおいて欠かせません。自社の商品やサービスを他社やお客さんに売り込む際に、必ずと言っていいほどプレゼンテーションが求められるからです。例えばA社とB社が似たような製品を売っている場合、プレゼンテーションのよしあしが選ばれる理由に直結することもあります。2.自分自身をしっかりとアピールするため上司や部下に自分自身を積極的にアピールするうえでも、プレゼンスキルは必須です。例えば、新しい部署が新設されたり、追加で業務ができたときに、誰にお願いするかは非常に重要です。そういった場面のときに、自分自身がなぜやりたいのか、どのように貢献できるのかを伝え、逆に、誰かにお願いする際には、なぜその人にやって欲しいと考えているのか、といったアピールにもプレゼンスキルが役立ちます。3.自分の成果をしっかり相手に伝えるため自分の成果をしっかりと相手に伝えるために、プレゼンテーションスキルは欠かせません。これまでに自分が行った活動や仕事内容を、端的に正確に伝えることで、自分自身への正当な評価につながります。せっかく丁寧に仕事をしていたとしても、伝え方が悪ければ損をしてしまう可能性があります。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 良いプレゼンとは?良いプレゼンテーションとはなんなのでしょうか?より良いとされるプレゼンテーションの特徴は3つあります。1.内容が簡潔でわかりやすいより良いプレゼンテーションをするには、資料の内容が簡潔でわかりやすいことが大切です。資料内の文章や説明が長いと、聞いている側はプレゼンの要点がどこにあるか分かりづらく、途中で飽きられてしまう可能性があります。そのため、プレゼンの内容をなるべく簡潔に伝える工夫をすることが大切です。2.主張が明確になっているプレゼンテーションをするうえで、自分の主張したいことははっきりと伝えましょう。主張したい事柄を強調していないプレゼンは、自分が本当に伝えたいことが上手く伝わらなかったり、誤って伝わってしまったりといったリスクが生じます。プレゼンテーションは自分の意思や意見、やってきたことなどを伝える場なので、はっきり自分が伝えたいことを主張することが重要です。3.説明が聞きやすく理解しやすいはきはきと喋ったり、適切な声量で伝えたりといったことを意識すると、プレゼンテーションを聞いている側は聞き取りやすく、内容も理解しやすいです。自分が思っていることや主張したいことを相手に届けるためにも、喋り方や声量にも工夫して話すことが大切です。高校生が磨くべきプレゼンスキル3つ続いては、高校生が磨くべきプレゼンスキルについて解説します。プレゼンテーションのスキルはたくさんありますが、最低限下記の3つを習得しておきましょう。1.傾聴力プレゼンスキルと聞くと「人前に立ち、スライドを使いながら自分の考えやアイデアを伝える力」というイメージが思い浮かぶ人は多いでしょう。これは間違いではありませんが、自分が話すだけがプレゼンではありません。相手の話を聞いたり反応を見たりしながら伝え方を変える力も欠かせません。そのために必要なのが傾聴や観察の力です。傾聴とは相手の話を真摯な姿勢で「聴く」ことです。耳だけでなく目線や身振りも使い「私はあなたの話を真剣に聴いていますよ」ということを伝えたり、相手の様子を観察して相手のことを理解したりします。信頼関係を築きながら相手の本音を引き出していくためのスキルで、もともとはカウンセリングでよく使われていましたが、最近ではビジネスシーンでも活用されています。1対1での対話に役立つスキルで、営業活動や商談の場ではもちろん、マネジメントやプライベートシーンにも活用できるでしょう。高校生のうちから相手の話を真剣に聴く姿勢を身につけることで、社会に出てからも円滑なコミュニケーションができるようになるはずです。2.人前で話す力人前で話す力も、これから生きていくうえでとても大切です。社会に出てからはもちろん、高校生活のなかでも人前で話す機会は少なからずあるはずです。社会に出ていきなり人前で話すことになったときに、慌てずにしっかりとプレゼンできるようになるためにも、学生のときからなるべく場数を踏んで、慣れておくことをおすすめします。3.論理的思考力さまざまな物事について論理立てて考える、論理的思考力も高校生のうちから磨いておきましょう。日常生活にあるあらゆる物事やできごとについて、なぜそうなっているのかを自分の頭を使って考えたり、友達と議論をしたりすることをおすすめします。日常生活の身の回りの何気ないことに対して「なぜ?」と疑問を持って答えを考えてみることで、論理的思考力は少しずつ鍛えられるので、ぜひすぐに取り組んでみてください。高校生がプレゼンテーションスキルを磨く方法3ステップ最後に、高校生がプレゼンテーションスキルを磨くための3ステップについて解説します。【ステップ1】お手本とするプレゼンテーションをたくさん見るまずは自分がお手本にしたいプレゼンテーションを探して見つけてみましょう。尊敬する人がいれば、その人が実際に行っているプレゼンテーションを真似てみるのもおすすめです。お手本となるプレゼンテーションの探し方として、YouTubeでの検索や、検索エンジンの活用がおすすめです。【ステップ2】本番を意識してたくさん練習してみるお手本となるプレゼンテーションを見つけたら、それを真似してたくさん自分で練習することが大切です。そのためにまず、お手本となるプレゼンテーションの良かった点を紙に書き出すなどして言語化してみましょう。そのうえで、良かった点を意識しながらプレゼンテーションの練習をします。練習時には、可能であればビデオ録画をしておきましょう。後から自分のプレゼンテーションを振り返る際に役立ちます。何度も練習を繰り返すことで、確実にプレゼンテーションスキルを伸ばすことができます。【ステップ3】学校内外で行われている各種プレゼンテーション大会に参加してみるある程度プレゼンテーションスキルが上達したと感じたら、実際に学校内外で開催されている各種プレゼンテーション大会に応募して出場してみましょう。プレゼンテーション大会の緊張感は特別です。いつもの練習では味わえない独特の雰囲気が漂っており、実際にその中でプレゼンテーションをすることで経験値はもちろん自信も身につきます。大会で賞を受賞すれば、自分の実績にもなります。高校生のうちからプレゼンテーションスキルを身につけておこう良いプレゼンテーションの特徴やプレゼンテーションスキルの身につけ方などについて解説しました。プレゼンテーションスキルを身につけることで、自分が本当に伝えたいことを、相手に誤解なく伝えられるようになります。また、自分自身の正当な評価にもつながります。高校生のうちから少しずつプレゼンスキルを身につけていくと、将来必ず役に立つのでぜひ少しずつトライしてみてください。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */}
READ MORE
![alt]()
【高校生必見】若い頃から身につけておくべきビジネススキルとは?
ナレッジ
社会に出て活躍するためには、最低限必要のビジネススキルが必要です。大学生や社会人はもちろん、高校生のうちからビジネススキルを学んでおくことで、高校卒業後の進路選択の幅が大きく広がります。そこで本記事では、高校生のうちから身につけておくと、将来役に立つビジネススキルについて解説します。ビジネスに役立つスキルや視点を身につけるための、高校生におすすめの教育プログラムも紹介します。より早く成長したい方や、高校生のうちから自分でビジネスをしたいと思っている方は必見の内容なので、ぜひ最後までご覧ください。 ビジネススキルとは明確な定義はないものの、ビジネススキルとは社会で働くうえで大切な知識やマナーなどを集約したスキルの総称です。ビジネススキルは学校では教えてもらえないため、自ら主体的に動きながら学ぶしかありません。また、ビジネススキルは社会に出てから必ず必要となるため、早めに身につけておくと良いでしょう。ビジネススキルを身につけることで、自分自身の人生の可能性を広げ、選択肢を増やすことができます。 高校生のうちから身につけておくと役立つビジネススキル5つ高校生のうちから身につけておくと役に立つビジネススキルは、大きく分けて以下の5つがあります。1.ビジネスマナー社会人として将来働くうえで絶対に欠かせないのが、ビジネスマナーです。ビジネスマナーは、さまざまなシーンで求められる常識的なマナー全般を指します。ビジネスマナーを理解していないと、仕事先でのお客さんの信頼を失ってしまったり、会社内の自分自身への評価が下がってしまったりするかもしれません。名刺の渡し方や基本的な言葉遣い、挨拶の仕方、上座・下座の理解だったりと、マナー内容は多岐に渡りますが、ひとつずつ習得していくことで、相手に失礼のないふるまいができるようになります。 2.コミュニケーションスキルコミュニケーションスキルも、他者と仕事をするうえで不可欠なスキルです。どんな仕事だろうと、必ず他者が関わっています。そこで適切なコミュニケーションが取れなければ、信頼を失ってしまいます。また、組織に属して働く場合には、より円滑にものごとをすすめるうえでも、適度なコミュニケーションはとても大切です。相手の気持ちを想像する力や、空気を読む力、誤解なく物事を伝える力など、場面に応じたコミュニケーションスキルは必ず身につけておきましょう。 3.基本的なPCスキル高校生のうちから基本的なPCスキルを身につけておくだけで、今後役立つ場面が増えるはずです。関わる職種や業務によっても異なりますが、WordやExcel、Power Pointなどが使えるだけで書類作成や各種データの管理などができるようになり、幅広い仕事で役立ちます。 4.問題解決力問題解決能力は日常生活において、意識を変えて行動することで高められるビジネススキルです。仕事をしていると、必ずといっていいほど何かしらの問題が生じます。その際、社会に出ると、どうしたら解決できるのかを自分の頭で考えて、提案することが求められます。これはなにも仕事だけに限らず、日常生活のなかにもあらゆる問題が潜んでいます。例えば、トラブルで集合時間に遅刻しそうになったり、なにかしら必要なものを忘れてしまったりしたときなどです。そういったときに、いかに問題解決のための改善策を考えられるかどうかがとても大切ですし、それは企業や世間からとても評価されます。そのため、高校生のうちから、身の回りのあらゆる問題に対して意識的に向き合い、問題解決能力を高めておくことが重要です。 5.プレゼンテーションスキルプレゼンテーションスキルを高めておくことで、あらゆる仕事に活かせます。プレゼンテーションスキルとは、しっかりと自分の言葉で、説得力を持たせて話せる力のことです。プレゼンテーションと聞くと、多くの人の前で講演や演説をするイメージを持たれがちですが、大勢の聴衆の前で話すことだけがプレゼンテーションスキルではありません。仕事をしていると、プロジェクトを推し進める際などに、周りの人に対して、論理的に正確な情報を伝える力が必要になります。場合によっては、他者を説得しなければいけない場面もあります。その際に、プレゼンテーションスキルがあると、役に立つのです。 高校生がビジネススキルを身につけるために必要なこと5つ高校生がビジネススキルを身につけるためには何が必要なのでしょうか?大きく分けて、主に5つあります。 1.実務を経験してインプットする高校生に限らず、手っ取り早くビジネススキルを身につけるには、実務を経験してインプットすることが大切です。学校内やバイト先、プライベートで、自分が尊敬していたり、憧れていたりする人がいる場合にはその人の行動をよく観察して、尊敬できる部分を真似てみるといいでしょう。また、普段から意識している行動や言動について聞いてみるのもおすすめです。お休みの日などを利用して、事前に承認を得た上で勉強のために一緒に働かせてもらうのも良いでしょう。 2.研修やセミナーに参加する全国各地やオンラインで開催されている、ビジネススキルやマナーに関する研修やセミナーに参加するのも、有効な手段です。特にオンラインの場合は、時間や場所の制約を受けずに参加でき、かつ場合によっては後から録画視聴で振り返ることもできます。研修やセミナーは少なからず参加費がかかる場合がありますが、ビジネススキルの基礎からしっかりと学べるケースが多い点が魅力です。 3.ビジネス書籍を読むビジネス書をたくさん読むことで、ビジネスの基礎や考え方が学べるのはもちろん、ビジネスに関するあらゆる情報が得られます。高校生・大学生の場合には通学中や学校終わりに、会社員の方であれば通勤中や仕事終わりなどの隙間時間に勉強可能です。自分のペースで少しずつビジネススキルを学びたい人におすすめです。 4.高校生向けのインターンシップに参加する高校生の方であれば、高校生向けに開催されているインターンシップに参加してみるのも良いでしょう。実際に企業に出社し、社員と一緒に働いてみることで、基礎的なビジネススキルはもちろん、働くことの意義や大変さも痛感できます。すでに社会に出ている先輩から話を聞くことでキャリアの幅が広がり、実体験を通してしか得られない学びもあるでしょう。 5.高校生向け教育プログラムに参加するビジネスや働き方について学べる高校生向けの教育プログラムに参加するのもおすすめです。最近はオンラインで参加できるプログラムが増え、放課後の時間を使ってビジネスについて気軽に学べます。たとえば「はたらく部」は全国の中高生が集まる「オンライン部室」のある教育プログラムです。会社員や起業家からYouTuberまで、第一線で活躍するさまざまな職種の現役社会人がコーチとなり、一人ひとりの挑戦や進路形成を後押しします。放課後に参加できるオンライン講義や対話型の実践的なワークショップを通して、生きる力を身につけられるでしょう。オンラインで参加できる無料体験会もあります。全国どこからでも都合の良いタイミングで参加できるので、ぜひ一度遊びに来てください。 詳しくはこちら:はたらく部 | 放課後集まる、未来の選択肢。高校生のうちからビジネススキルを身につけよう高校生の頃から身につけておくとよいビジネススキルや、学び方について解説しました。既に働いている方は当然かもしれませんが、今後社会に出て働くうえで最低限のビジネススキルは必須です。ビジネススキルは早く身についておいて損はありません。実際に企業にインターンシップに行ったり、ビジネス書籍を読んだり、研修やセミナーに参加したりして、自己研鑽に励みましょう。ぜひ本記事を参考に、ビジネススキルの習得を目指してみてはいかがでしょうか。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */}
READ MORE
![alt]()
中卒の進路は高校以外もある?中卒者の進路選択
ナレッジ
「中卒の進路の選択肢は何種類?」と問われて、即答できる人はどのくらいいるでしょうか。後の資料でもお見せしますが、多くの人は中卒後の進路として「進学」を選択しています。しかし、義務教育が終了する中学卒業後の進路は、周りの意見ではなく、本人自らが選択するのが好ましいのではないでしょうか。今回は、中卒の進路にはどんなものがあるか一緒にみていきながら、自分の進路について考えてみてほしいと思います。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 中卒の現状「進学」最初に中卒者の進路について、現状を次の資料を参考に確認していきます。
READ MORE
![alt]()
卒業後の進路は決まってる?高校・大学の卒業後の進路選択
ナレッジ
卒業後の進路について、本格的に悩みだすのは高校生か大学生くらいでしょうか。早い人は中学生の頃に進路で悩む人もいるかもしれません。中学生の頃は、例えば普通科や総合学科といった選択肢を広く持てる進学先を選ぶことで、考える時間を得ることもできます。しかし、高校や大学の卒業後の進路は、将来に大きな影響を与えます。今回は、そんな高校や大学の卒業後の進路について一緒に考えてみましょう。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 卒業後の進路状況高校生や大学生が卒業後にどんな進路を選択しているのか、文部科学省が毎年実施している「学校基本調査」令和4年度の資料を参考にみていきます。 高校生の卒業後の進路状況最初に高校生の卒業後の進路状況をみていきます。
READ MORE
![alt]()
高校生の「進路が決まらない」問題・悩み別の解決方法を解説
ナレッジ
高校生になると「進路が決まらない」という悩みを抱える人も出てくるでしょう。中学生の頃は「とりあえず進学!」という決め方もできますが、高校生になると中学生の頃よりも選択肢が増えますし、より将来を見据えた選択を迫られます。今回はそんな悩みを抱える高校生へ向けて、悩み別の解決方法や向き合い方を説明します。.banner-link { display: block; width: 100%; max-width: 1200px; /* バナーの最大幅を設定 */ margin: 0 auto; /* 中央寄せ */ transition: all 0.3s ease; /* ホバーエフェクトのアニメーション */ text-decoration: none; /* 下線を削除 */ position: relative; /* カーソルエフェクトの基準位置 */ cursor: pointer; /* ポインターカーソルを表示 */}.banner-link:hover { opacity: 0.8; /* ホバー時の透明度 */ transform: translateY(-3px); /* ホバー時に少し上に浮く */}.banner-link::before { content: ""; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 0; height: 0; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; transform: translate(-50%, -50%); transition: width 0.3s, height 0.3s; pointer-events: none; /* カーソルイベントを無効化 */ z-index: 1;}.banner-link:hover::before { width: 100px; height: 100px;}.banner-image { width: 100%; height: auto; display: block; /* 画像下の余白を削除 */ border-radius: 4px; /* 画像の角を少し丸く */ box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影をつける */} 高校生の進路・将来に対する意識高校生の「進路が決まらないという悩み」や「進路が決まらない理由」について、一般社団法人全国高等学校PTA連合会と、株式会社リクルートマーケティングパートナーズが合同で調査した「第9回 高校生と保護者の進路に関する意識調査 2019年 報告書」を参考にみていきます。高校生の進路意識「進路についてどのくらい考えているのか」ここでは高校2年生時点での意識を調査し、次のような結果が出ました。
READ MORE
RePlayce, Inc. ©2025. All Rights Reserved